仕上塗材と下地調整材のアスベスト調査には層別分析が不可欠

建築物の外装や内装に使われる仕上塗材はセメントや合成樹脂などの結合材、顔料、骨材などを原料とします。かつて、アスベスト(石綿)は添加材として使用されていました。
アスベストを長期間吸引することで健康被害につながることが問題となり、2006年の労働安全衛生法施行令の改正で製造や輸入、使用などが全面的に禁止となりました。しかし、それ以前に建築された建物については、仕上塗材にアスベストが含まれている可能性があり、改修や解体工事の際に適切な対応が必要です。
同じく過去にアスベストが使用された下地調整材も含め、アスベスト含有の仕上塗材について理解を深めながら、アスベスト調査の有効な方法やアスベスト含有が判明した場合の対応などについて紹介します。
【本記事の要約】
・2006年以前に施工された仕上塗材や下地調整材にはアスベスト含有の可能性がある
・幾層にも重なる仕上塗材や下地調整材は層別分析でアスベストを含む層の特定が必要
・仕上塗材や下地調整材にアスベスト含有が判明した場合は適切な処理工法を選定する
- 1. 仕上塗材とは
- 1.1. アスベスト含有仕上塗材の種類
- 1.2. 軽量塗材はレベル1の作業基準を適用
- 2. アスベスト含有の可能性が高い下地調整材とは
- 2.1. アスベスト含有下地調整材の種類
- 2.2. アスベスト含有下地調整材の作業基準は仕上塗材とは異なる
- 3. 仕上塗材、下地調整材に有効なアスベスト調査は層別分析
- 3.1. 層別分析とは
- 4. 仕上塗材、または下地調整材にアスベスト含有が確認されたら
- 4.1. 除去作業の前に自治体の条例を確認
- 4.2. 除去作業には湿潤化が必要
- 4.3. アスベスト含有仕上塗材の処理工法は主に3種類
- 5. 幾層にも分かれている仕上塗材の事前調査には層別分析を
仕上塗材とは
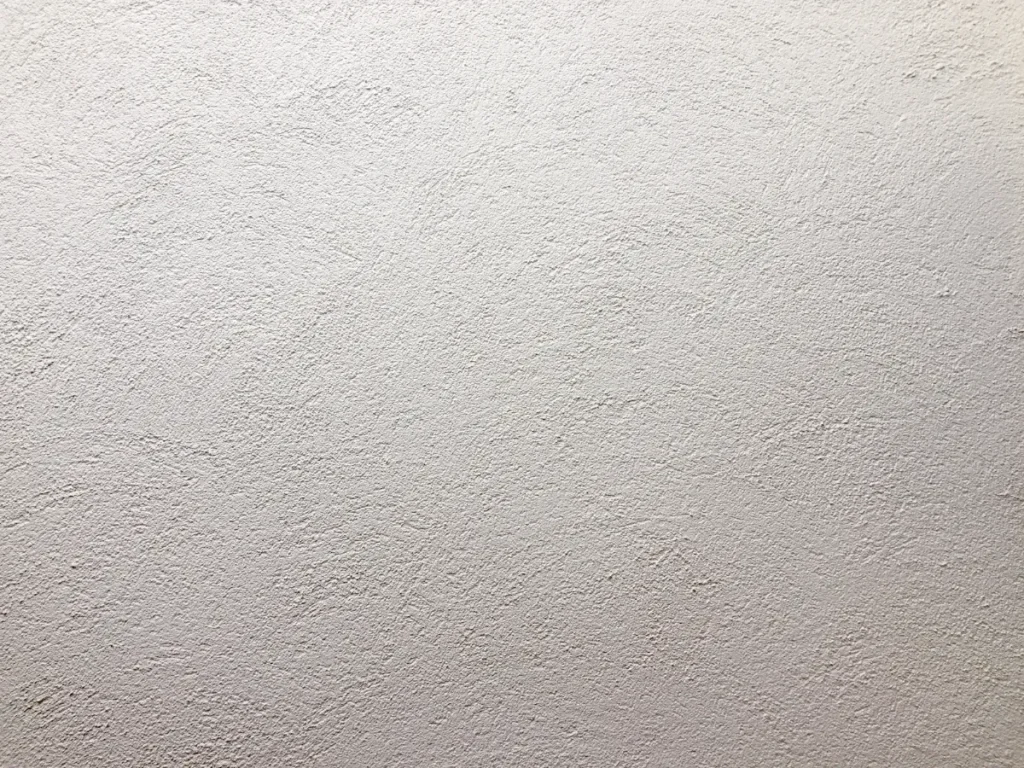
建築用仕上塗材とは、建築物の外装や内装に使われる塗装材料または左官材料です。一般的な塗料が数十ミクロンほどの厚さであるのに対し、仕上塗材は数ミリ単位の厚さを形成するもので、吹き付けやこて塗り、ローラー塗りなどによって造形的な模様や質感に仕上げることができます。
セメントや合成樹脂などの結合材、顔料、骨材を原料とする仕上塗材ですが、塗膜のひび割れや施工時のダレを防止するため、主材の中にクリソタイル(白石綿)やアモサイト(茶石綿)、トレモライトを添加材として少量使用していた時期がありました。
仕上塗材に含まれるアスベストはセメントなどの結合材で固められており、塗膜が健全な状態であればアスベストが飛散するリスクは低いとされています。しかし、改修や解体工事などで除去する場合は破断を避けられないことが多く、除去方法によっては飛散する可能性があり、取り扱いに注意が必要です。
アスベスト含有仕上塗材の種類
アスベスト含有の仕上塗材には、主に下塗材と主材のみの薄付けで砂壁模様を造る薄塗材C(セメントリシン)や薄塗材E(樹脂リシン)、同じく薄付けで内装の壁や天井に使われた内装薄塗材Si(シリカリシン)や内装薄塗材E(じゅらく)、主に下塗材と主材、上塗材の3回塗り重ねる複層塗材C(セメント系吹付けタイル)や複層塗材E(アクリル系吹付けタイル)、厚付けで3回前後塗り重ねる厚塗材C(セメントスタッコ)や厚塗材E(樹脂スタッコ)、パーライトなど軽量骨材を混ぜた軽量塗材(吹付けパーライト)など、全18種類が確認されています。販売期間は1970〜1999年で、アスベスト含有量は少ないもので0.1%、多いもので5.0%になります(軽量塗材を除く)。
アスベストを含有する建築材料のレベル分類では、以前は吹付けアスベストと同じ飛散性が高いとされるレベル1でしたが、2020年に大気汚染防止法が改正されたことにより、飛散性が低いとされるレベル3になりました。
軽量塗材はレベル1の作業基準を適用
先に述べたアスベスト含有仕上塗材の種類の中で、軽量塗材は「吹付けパーライト」「吹付けバーミキュライト」と呼ばれるもので、屋内の天井などに施工されました。販売期間は1965〜1992年と比較的長く、アスベスト含有量は0.1〜24.4%になります。これらの軽量塗材は飛散性が高いとされ、大気汚染防止法の改正後も変わらず吹付けアスベストに分類されたままとなっており、除去時の飛散防止措置もレベル1の作業基準が定められています。
アスベスト含有の可能性が高い下地調整材とは

仕上塗材を施工する前処理として、コンクリートの不陸部分などを平坦にする目的で塗られるのが下地調整材です。過去に使用されたアスベストは多くがクリソタイルで、ごく一部にアモサイトも使われました。仕上塗材と同じくセメントなどの結合材で固められているため、通常の環境下ではアスベストが飛散する可能性はないと考えられますが、除去工法によっては飛散のおそれがあります。
アスベスト含有下地調整材の種類
アスベストが使われた下地調整材には「下地調整塗材C(セメント系フィラー)」と「下地調整塗材E(樹脂系フィラー)」の2種類があります。販売期間は1970〜2005年、含有量は0.1〜6.2%とされています。アスベスト含有の仕上塗材は1992年に販売を終了しましたが、下地調整材は2005年まで販売が続いたことから、過去の建築物において下地調整材のアスベスト含有の可能性は高いと考えられます。
※仕上塗材・下地調整材の種類、販売期間、含有量については「日本建築仕上材工業会」が会員会社を対象に行ったアンケート調査をまとめたもので、網羅性や正確性が保証されたものではありません。
アスベスト含有下地調整材の作業基準は仕上塗材とは異なる
厚生労働省と環境省のマニュアルが統合された「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」では、下地調整材は仕上塗材として区分されていますが、法令上はアスベスト含有成形板等の作業基準が適用されます。
アスベスト含有成形板等は、セメントなどとともに成形されたアスベスト含有建材で、屋根のスレート波板、外壁のスレートボードや窯業系サイディング、内壁・天井のスレートボートやパーライト板、石膏ボード、床のビニルタイル・シートなどの材料に使われています。
下地調整材に含まれるアスベストはセメントなどによって固められているため、通常は飛散する可能性は極めて低いとされています。ただし、除去時に切断や破砕作業によって飛散する可能性が高く、アスベスト含有成形板等の除去作業における飛散防止対策を実施することが必要です。
仕上塗材、下地調整材に有効なアスベスト調査は層別分析

仕上塗材は幾層にも複雑に重なっており、その下には下地調整材が塗られています。一部の層にのみ比較的低濃度のアスベストが含まれている場合、全体が混ざってしまうと検出が困難になるケースもあります。
アスベストが含まれるのは主に仕上塗材の主材と下地調整材です。事前調査では、アスベストを含む箇所が仕上塗材(主材)なのか、下地調整材なのか、もしくはその両方なのかを区別し除去方法を検討する必要があります。そのためには層別分析が有効です。
層別分析とは
アスベスト含有を調べる分析方法には「定性分析」と「定量分析」があります。アスベストの有無を調査できる定性分析には2種類あり、実体顕微鏡と偏光顕微鏡を使ってアスベストの形状や色、光学的性質などを観察できる「JIS A 1481-1」では、層別分析に対応しています。もう一方の「JIS A 1481-2」はX線回析装置と位相差・分析顕微鏡を使ってアスベストの有無と種類を判定する分析方法ですが、含有する層は特定できません。
定性分析でアスベスト含有が認められた場合、X線回析分析法を用いてアスベストの含有量を調べる「定量分析」によって、その濃度を調べることができますが、実際に定量分析で詳細の含有量が分かったとしても0.1%を超えた際の法律の対応は一律ですので、定量分析を求められるケースは非常に限定的です。
ドライアウトなどが原因で仕上塗材と下地調整材が一緒に剥離する場合もあるため、分析試料の採取にあたっては劣化状態や工事内容を理解したうえで行うことが重要です。
仕上塗材、または下地調整材にアスベスト含有が確認されたら

建築物の改修・解体工事を行う場合、一部の例外を除いてアスベスト含有の事前調査を実施し、その結果を都道府県に報告する義務があります。質量の0.1%を超えるアスベストが確認された場合は、アスベスト飛散防止対策を講じながら除去作業を行わなければなりません。除去後は廃棄物処理法に基づき、アスベスト含有廃棄物として適切に処理を行います。
除去作業の前に自治体の条例を確認
2020年の大気汚染防止法の改正によって、アスベストを含有する仕上塗材の除去作業は工法を問わず一律に規制の対象になりました。遵守すべき作業基準が設けられ、仕上塗材特有のアスベスト飛散防止法が示されています。
同法の改正で、アスベスト含有仕上塗材の除去作業を都道府県に届け出る必要はなくなりました。ただし、作業計画の作成、各種掲示・表示、作業状況の記録・保存、作業完了の確認、作業種別の基準遵守、事業発注者への説明などは必要です。
また、自治体によっては条例などで届出を必要としているところもあります。仕上塗材にアスベスト含有が認められた場合は、自治体の条例なども併せて確認しましょう。
除去作業には湿潤化が必要
アスベストを含有する仕上塗材の除去作業では、大気汚染防止法や石綿障害予防規則によってアスベスト飛散防止の措置が必要です。切断などを行わず、原型のまま取り出すことが原則ですが、困難な場合は切断面などへの散水を行うなど、常時湿潤な状態を保つことが求められます。あるいは、除じん性能を持つ電動工具の使用や粉じんの発生防止措置(剥離材の使用を含む)を講じることでも対応できます。
アスベスト含有の下地調整材は原型のまま取り出すことが難しいため、同様に湿潤化が必要になります。どちらも湿潤化に使った水にはアスベストが含まれるため、排出される水を回収し排水処理を行います。
アスベスト含有仕上塗材の処理工法は主に3種類
アスベスト含有の仕上塗材を除去する処理工法は、国立研究開発法人建築研究所および日本建築仕上材工業会が作成した「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術方針」に15種類が紹介されています。
主に、水による湿潤化と仕上塗材の除去を一体的に行う「高圧水洗工法」、剥離材で軟化させて除去する「剥離材を用いる工法」、除じん性能のある電動工具で切断などを行う「電気グラインダー等を使用する工法」の3つに分類されます。
処理工法の選定では、可能な限り粉じんが発生しない工法を選ぶことが大切です。また、剥離材を使って除去する場合は、残った剥離材が新しく施工する仕上塗材に悪影響をおよぼす可能性があります。仕上塗材の改修では、改修材料や工法を把握して実施することが重要です。
参考:建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術方針https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/171/3.pdf
幾層にも分かれている仕上塗材の事前調査には層別分析を
仕上塗材は、下地調整材、下塗材、主材、上塗材など幾層にも複雑に重なっています。改修・解体工事ではアスベストの有無を調査することはもちろん、アスベストが確認された場合は含まれている層まで特定することが重要です。アスベスト含有の仕上塗材や下地調整材はレベル3の作業基準となりますが、吹付けパーライトなど軽量塗材はレベル1の作業基準が求められます。どの層にどの材質のアスベスト含有仕上塗材が使用されているか、正確に分析できる専門機関に調査を依頼したいところです。
アスベスト分析を依頼する際には、調査機関の品質(分析精度)に注意する必要があります。アルフレッドでは、分析における見落としなどが生じないための、分析プロセスや最新のITシステムを導入しております。詳細は以下のラボ紹介動画からぜひご覧ください。
また、99.998%の驚異的な納期遵守率による安定した納期や現場からスマホで発注ができる「アルモバ」サービスをご体感いただくためにも、初回最大10検体までの無料キャンペーンも行っております。これを機に、ぜひお試しください。

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。
お役に立ちましたら、ぜひ関係者様にシェアをお願いします /
新着記事






