アスベストの危険性とは?見落としやすいリスクと安全対策の要点

アスベストが危険な物質であることは、建設・改修に携わる事業者にとって周知の事実です。しかし、なぜ危険なのか、その理由を知っている方は多くはありません。この「なぜ」を知ることが、さまざまな安全対策の狙いや重要性を明確にし、万全なリスク管理へと繋がります。
現在も多くの建物に潜むアスベストは、解体や改修時に飛散するリスクを伴います。見落とされがちなその危険性から身を守り、新たな健康被害を防ぐためにも、今一度アスベストの特性と対策について学び、適切な知識を現場に活かしてください。
【本記事の要約】
・アスベストは繊維の吸入が危険なため飛散防止対策が法律で定められている
・含有建材は飛散のしやすさによってレベル分けされ、対策法が異なる
・事前調査による識別と除去後の確認作業も危険防止に欠かせない
- 1. アスベストはなぜ危険なのか
- 1.1. 日本におけるアスベスト規制の歴史
- 1.2. 繊維の性質と健康への影響
- 1.3. 飛散リスクと作業時の注意点
- 2. 使用実態とレベルごとの危険性
- 2.1. 【レベル1】吹付けアスベストなど
- 2.2. 【レベル2】保温材・断熱材など
- 2.3. 【レベル3】スレート・Pタイル・石膏ボードなど
- 2.4. ロックウール・グラスウールの危険性
- 3. アスベスト対策の基本
- 3.1. アスベストの識別の重要性
- 3.2. 事前調査の実施と有資格者の役割
- 3.3. 飛散防止と作業現場での基本対策
- 3.4. 除去作業後における安全管理
- 4. 4. アスベスト被害と救済制度
- 4.1. 職業性ばく露が多い背景
- 4.2. 救済制度と申請の概要
- 5. 事前調査でアスベストを見抜くことが危険防止の第一
アスベストはなぜ危険なのか

アスベストは、その優れた特性からかつては「奇跡の鉱物」とまで称され、建材を中心に幅広く利用されてきました。しかし、その微細な繊維が人体に及ぼす深刻な健康被害が明らかになってからは、各国でその使用が厳しく規制されています。特に、解体や改修工事では、見えないリスクへの正確な理解と、厳格な飛散防止対策が不可欠です。
日本におけるアスベスト規制の歴史
アスベストは、断熱性、耐火性、防音性、そして耐久性に優れるため、1970年代から1980年代にかけて、日本でも多くの建築物に使用されてきた天然の繊維状鉱物です。
しかし、アスベスト粉じんの吸引による健康被害が世界的に社会問題化したことを受け、日本でも1975年に特定化学物質等障害予防規則で規制が始まりました。その後、段階的に規制は強化され、2006年9月には労働安全衛生法施行令によって、0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用は、全面的に禁止(一部の工業製品は2012年まで猶予期間あり)となっています。
繊維の性質と健康への影響
アスベストは、髪の毛の約5,000分の1の細さともいわれる非常に細かく軽量な繊維で構成されており、空気中に浮遊しやすく、吸入されることで肺に深く沈着します。長期にわたるばく露により、中皮腫や肺がん、アスベスト肺などの重篤な疾病を引き起こすことが確認されており、特に数十年の潜伏期間を経て発症する点が大きな特徴です。
飛散リスクと作業時の注意点
静置されている状態でのリスクは限定的ですが、解体、改修、補修、または損傷により建材が破壊されると、その繊維が空気中に大量に飛散し、ばく露リスクが著しく高まります。中でも、吹付けアスベストやアスベスト含有保温材などは、摩擦や振動といったわずかな刺激でも繊維が飛散しやすいため注意が必要です。
これらの建材を取り扱う際には、作業員だけでなく、周辺住民への影響も考慮した厳重な飛散防止対策の徹底が求められます。作業現場では、アスベストが飛散する可能性のある作業を特定し、適切な保護具の着用、作業区域の隔離、湿潤化などの措置を徹底することが、ばく露を最小限に抑える上で極めて重要です。
使用実態とレベルごとの危険性

アスベスト含有建材は、飛散性の高さに応じてレベル分けされています。一般的に、飛散しやすいアスベスト含有建材は「レベル1」、やや飛散しやすいものは「レベル2」、飛散しにくいものは「レベル3」です。
日本の建築物では、屋根材、壁材、断熱材、床材など、広範な箇所でアスベスト含有建材が使用されており、特に1970年代から1990年代初頭に建設された建物では、その含有リスクが高いとされています。これらの建材の適切な識別と、レベルに応じた対策が安全な工事には不可欠です。
【レベル1】吹付けアスベストなど
レベル1のアスベスト含有建材は、最も飛散性が高いとされるものです。代表的なものとしては、耐火性や断熱性を高めるために天井や壁に吹付けられた吹付けアスベストが挙げられ、アスベスト含有吹付けロックウールなども含まれます。
これらは繊維が脆く、わずかな振動や衝撃で容易に空気中に飛散するのが特徴です。除去作業においては、作業区域の厳重な隔離、負圧除じん装置の設置、作業員の特殊な保護具の着用、湿潤化の徹底など、厳重な飛散防止措置が義務付けられています。除去後の清掃も、専用の高性能フィルター付き掃除機を使用するなど、徹底した管理が必要です。
【レベル2】保温材・断熱材など
レベル1に次いで飛散性が高いとされるのがレベル2の建材で、ボイラーや配管の保温材、煙突の断熱材などが該当します。
これらは、使用箇所が限定的ではあるものの、劣化したり、破損したりすると繊維が飛散するリスクが高まるのが特徴です。除去作業の際は、レベル1ほど厳重ではないものの、作業区域の養生、湿潤化、保護具の着用、フィルター付き掃除機による清掃など、十分な飛散防止対策が求められます。
【レベル3】スレート・Pタイル・石膏ボードなど
レベル3に該当するのは、アスベスト含有スレート板(屋根材や外壁材)やPタイル(床材)、石膏ボード、けい酸カルシウム板など、比較的飛散性が低い建材です。基本的にセメントなどで固められており、通常の状態ではアスベスト繊維が飛散しにくい構造が特徴となっています。
しかし、切断、穿孔、破砕といった作業を行うと、繊維が飛散する危険性があるため注意が必要です。除去作業においては、原則として建材を原形のまま取り外すことが求められ、粉じんの発生を抑えるための湿潤化や、局所排気装置の使用などが推奨されます。また、作業員は防じんマスクなどの保護具を着用する必要もあるので留意しましょう。
ロックウール・グラスウールの危険性
アスベストの使用禁止を受け、代替品として広く利用されているのがロックウールやグラスウールです。どちらも繊維の太さや形状がアスベストとは異なり、人体に吸入されたとしても肺の奥深くまでは到達しにくいため、深刻な健康被害を引き起こす可能性は低いとされています。
ただし、作業中に飛散した繊維が目や皮膚に刺激を与えたり、呼吸器に一時的な不快感をもたらしたりする可能性があるため、取り扱い時には保護具の着用や適切な換気を行うことを心掛けましょう。
アスベスト対策の基本

アスベストの危険性を理解するだけでは不十分で、現場ごとに適切な調査・隔離・除去・記録管理の実行が重要です。特に、解体・改修工事に携わる事業者にとっては、法令遵守はもちろんのこと、作業員と周辺住民の安全を確保するための確実な対策が求められます。
アスベストの識別の重要性
建築物にアスベストが使用されているかどうかは、外観だけでは判断が極めて困難です。そのため、改修や解体工事を行う前には、専門家による事前調査が不可欠となります。
事前調査では、建築図面や竣工図の確認に加え、実際に建材の一部を採取し、成分分析を行うことで、アスベストの含有の有無や種類、含有量などを正確に特定が可能です。この識別が不十分だと、知らずにアスベスト含有建材を損傷させ、繊維を飛散させてしまうリスクがあるため、初期段階での正確な情報把握が、その後の安全対策の要となります。
事前調査の実施と有資格者の役割
2022年の改正により、一定規模の解体・改修工事ではアスベスト含有の有無を調査することが法的に義務付けられました。この調査は専門資格を持つ調査者が実施し、結果は所轄官庁等に報告されます。調査の正確性と報告義務の遵守が、安全で合法的な工事の前提です。
また、2026年1月1日からは、これまで曖昧にされてきた一部の工作物の解体・改修工事におけるアスベスト事前調査についても、「工作物石綿事前調査者」による調査が義務付けられるので注意しましょう。
飛散防止と作業現場での基本対策
アスベスト含有建材の除去や封じ込め、囲い込みといった作業を行う際には、繊維の飛散を最小限に抑えるための徹底した対策が必要です。飛散防止措置としては、作業区域を隔離して他の区域への拡散を防ぎ、建材を湿潤化することで繊維の飛散を抑制するのが基本となります。
作業員は、粉じんの吸入を防ぐための防じんマスク(高性能フィルター付きのP3レベル以上)や保護衣、保護手袋などの適切な保護具を必ず着用します。さらに、作業区域内を負圧に保つための負圧除じん装置の設置や、作業後の入念な清掃も重要です。こうしたアスベストの対策は、作業員の健康だけでなく、周辺環境への影響も考慮しなくてはならないことを覚えておきましょう。
除去作業後における安全管理
除去後の区域は、アスベストが完全に除去されていることを確認するため、最終確認調査を行うことが労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則で義務付けられています。この調査で環境中のアスベスト濃度を測定したり、残存するアスベスト繊維がないかを視覚的に確認し、安全が確認された後に限り、作業区域の隔離を解除できます。
また、除去されたアスベスト含有廃棄物は、特別管理産業廃棄物に指定されており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、飛散しないように二重袋に梱包し、専用の容器に収納するなど、厳重な管理のもとで適正に運搬・処分しなければなりません。不適切な廃棄は、環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があるため、関連法令を遵守し、認可された専門業者に委託しましょう。
4. アスベスト被害と救済制度
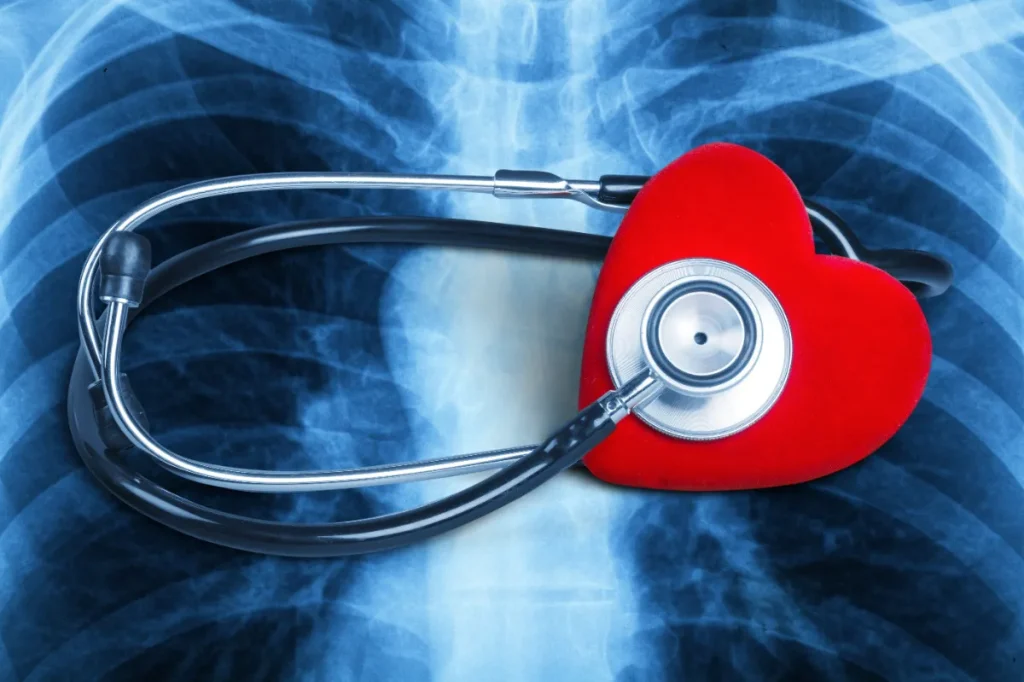
アスベストによる健康被害は、一度発症すると完治が難しい病気が多く、その被害は広範囲に及んでいます。特に、過去にアスベストを取り扱う機会の多かった職業に従事していた方々を中心に、現在も多くの健康被害が報告されており、その救済に向けて様々な制度が設けられています。
職業性ばく露が多い背景
建設業や製造業では、かつてアスベストが安価で高性能な建材として、あるいは製品の原材料として大量に使用されていました。そのため、これらの産業に従事していた労働者は、アスベスト粉じんにばく露する機会が極めて多く、長期的なばく露により健康被害を受けた事例が数多く報告されています。
現在も「建設アスベスト訴訟」が全国各地で続き、過去のアスベスト使用に起因する健康被害に対して、国や企業に対する賠償が争われているのが実情です。これは、アスベストによる健康被害が、決して過去のものではなく、現在進行形の問題であることを示しています。
救済制度と申請の概要
アスベストによる健康被害を受けた方々を救済するため、「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)」が2006年に施行されました。この法律に基づき、石綿関連疾病と認定された方々に対して、医療費の支給、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金などの給付金が支給されます。
制度の利用には、独立行政法人環境再生保全機構への申請が必要で、ばく露歴の確認や専門医による医学的診断、病理組織学的検査結果などが求められます。申請手続きや必要な書類について、詳しい情報は環境再生保全機構のウェブサイトで確認するか、専門家や弁護士に相談するとよいでしょう。
事前調査でアスベストを見抜くことが危険防止の第一
アスベストによる健康被害は過去の問題ではなく、現在進行形です。過去にばく露した方々への救済制度は存在しますが、建築物の解体・改修に関わる事業者や企業として最も重要なのは、適切な知識と最新の法令に基づいた対策で、新たな健康被害を未然に防ぐことです。
そのためには、何よりもまず事前調査によるアスベストの正確な識別が欠かせません。有資格者による綿密な調査で、アスベストの有無、種類、飛散性に応じたレベル(レベル1~3)を特定し、その情報に基づいた適切な除去・飛散防止対策の徹底が求められます。
アルフレッドは、最新鋭の分析設備を備えたラボで、高精度な分析を実施。土曜日を含め、安定して3営業日以内に分析結果をご提供します。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成にも対応。面倒な作業もお任せください!
初回発注の方には、最大10検体までの無料キャンペーンを実施中です。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。
お役に立ちましたら、ぜひ関係者様にシェアをお願いします /
新着記事






