アスベストを含む廃棄物の処理方法|収集・運搬から管理、最終処分まで

浮遊した繊維を長期にわたって大量に吸入することで、健康被害を引き起こす可能性が高いアスベスト(石綿)。そのため、古い建築物の解体・改修を行う際はアスベスト含有建材の有無を確認し、必要に応じて法律に則った飛散防止対策を講じなければなりません。
さらに、解体・改修のみならず、その後に発生するアスベスト含有廃棄物の運搬方法や処理の仕方まで厳密に規則が定められています。本記事では、そんなアスベストを含む廃棄物の処理方法について徹底解説します。不適切に処分した場合、関与した当事者はもちろん、依頼した業者まで罰則が科されるケースもあるので、解体・改修の作業に関わる方は法に定められた処理方法をしっかり把握しておくことが大切です。
【本記事の要約】
・アスベストを含む廃棄物は「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」の2種に区分される
・アスベストを含む廃棄物の収集・運搬から中間処理、そして最終処分までの流れを各工程でのポイントとともに把握できる
・法令違反による罰則などを科されないために理解しておくべき、アスベスト廃棄物を取り扱う上での注意点を確認できる
- 1. アスベストを含む廃棄物の種類
- 1.1. 「廃石綿等」に指定される飛散性アスベスト廃棄物
- 1.2. 「石綿含有産業廃棄物」に指定される非飛散性アスベスト廃棄物
- 1.3. 廃棄物処理における元請けの責任
- 2. アスベストを含む廃棄物の収集と運搬
- 2.1. 「廃石綿等」の収集と運搬
- 2.2. 「石綿含有廃棄物」の収集と運搬
- 2.3. 厚さ0.15 mm以上のプラスチック袋を使用
- 2.4. アスベストを含む一般家庭用品の場合は?
- 3. アスベストを含む廃棄物の中間処理
- 3.1. 「廃石綿等」の中間処理
- 3.2. 「石綿含有一般廃棄物」の中間処理
- 4. アスベストを含む廃棄物の最終処分
- 4.1. 「廃石綿等」の最終処分
- 4.2. 「石綿含有一般廃棄物」の最終処分
- 5. アスベストを含む廃棄物処理での注意点
- 5.1. 契約書の明確化
- 5.2. 処理業者の選定
- 5.3. 分別管理の徹底
- 5.4. マニフェストの交付・管理
- 6. 正しい知識と事前分析で廃棄物無駄を最小限に抑える
アスベストを含む廃棄物の種類
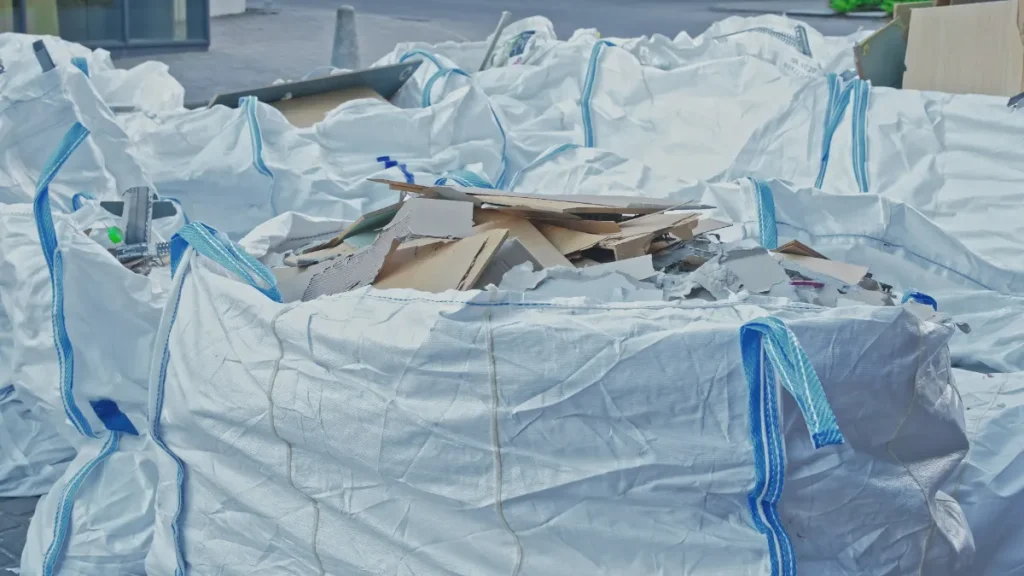
同じアスベストを含む廃棄物でも、飛散のしやすさによって「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」の2つに区分されるので注意が必要です。「廃石綿等」は飛散性が高いのが特徴で、「特別管理産業廃棄物」として分類され、取り扱いには高い安全性と専門的な処理が求められます。
もう一方の「石綿含有産業廃棄物」は比較的飛散の恐れは低いものの、一定濃度(重量比0.1%超)以上のアスベストを含む産業廃棄物として特別な管理が必要です。それぞれ処理の仕方が異なるため、まずは廃棄物を的確に分類するための知識を身につけましょう。
「廃石綿等」に指定される飛散性アスベスト廃棄物
「廃石綿等」には、吹付けアスベストやアスベスト保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材の他、人の接触や気流及び振動などによってアスベストが飛散する恐れのあるすべての保温材、断熱材、耐火被覆材が該当します。
また、除去工程で用いたプラスチックシートや防じんマスク、作業衣など、アスベストが付着している可能性が高い保護具や資材も「廃石綿等」に分類されるので注意してください。
「石綿含有産業廃棄物」に指定される非飛散性アスベスト廃棄物
「石綿含有産業廃棄物」に該当するのは、具体的には、スレート(波板、ボード)やパーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板など、実にさまざまな建材が当てはまります。
また、工作物の新築・改築・撤去により発生したコンクリートの破片などのがれき類、ガラスくず、陶磁器くず、廃プラスチック類、繊維くずなども「石綿含有産業廃棄物」に分類される場合があるので留意しておきましょう。
廃棄物処理における元請けの責任
産業廃棄物の処理責任は、原則としてその廃棄物を排出した事業者(排出事業者)にあります。排出事業者は、自らの責任において適切な処理を行うか、都道府県知事等の許可を受けた処理業者に処理を委託する義務が定められています。
処理を委託する場合でも、処理が適正に行われたかを確認する責任が残るため、契約内容や産業廃棄物管理票による厳格な管理が必要です。不適正な処理が判明した際には、排出事業者も責任を問われることがあるため、信頼性のある処理業者の選定と処理工程の管理が極めて重要です。
【アスベスト廃棄物処分に関する主な罰則一覧】
| 違反内容 | 罰則 |
| 無許可で運搬・処分、不正に許可更新、無許可業者への委託、不法投棄など | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または両方 ※法人には最大3億円の罰金 |
| 政令違反、業務の再委託、改善命令違反、不法投棄目的の運搬など | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、または両方 |
| 不法な輸出の準備 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金、または両方 |
| 機密情報漏えい、造成命令違反など | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 特別管理産業廃棄物の無届保管、施設の無検査使用、マニフェストの虚偽記載・未発行など | 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 帳簿の未記載・虚偽記載、施設変更未届出、検査拒否など | 30万円以下の罰金 |
| 業務無断休止、虚偽記載、検査拒否(職員・役員によるもの) | 30万円以下の罰金 |
| 廃棄物保管の無届出、計画書未提出、無断で地下に埋設など | 20万円以下の罰金 |
| 無許可業者が偽って業務表記 | 10万円以下の罰金 |
アスベストを含む廃棄物の収集と運搬

アスベスト廃棄物の収集と運搬には、飛散による健康被害や環境汚染を防ぐため、法律で厳格なルールがあります。特に飛散性のある「廃石綿等」は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者による対応が必須です。
一方で、飛散性が比較的低い「石綿含有産業廃棄物」は、通常の産業廃棄物収集運搬業者が対応します。正しい区分と許可のもとで、安全かつ確実な処理を実施してください。
「廃石綿等」の収集と運搬
廃石綿等の収集・運搬は、人の健康や生活環境に悪影響を与えないよう、厳重に管理して行う必要があります。まず、「廃石綿等」は他の廃棄物と混ぜず、別々に区分して扱うことが義務付けられています。その上で飛散や流出を防ぐため、密封したプラスチック袋を破損のないシートで覆うか、頑丈な容器に入れ、転倒や移動の防止策が必須です。容器が破損した場合には、散水などで飛散を防ぎ、排出事業者に速やかに連絡します。
また、運搬車には「産業廃棄物収集運搬車」である旨と許可情報を見やすく表示。許可証の写しや管理票も携帯し、取り扱いの注意点は文書で備え置くか、容器に明記する必要があります。
「石綿含有廃棄物」の収集と運搬
「石綿含有廃棄物」を収集・運搬する際は、破砕せず、他の廃棄物と混ぜないようにしっかり分けて扱い、飛散や流出が起きないよう厳重に管理する必要があります。
運搬車両は石綿含有廃棄物の形状に合った構造で、飛散防止用のシート等かけられるものを用意します。やむを得ず他の廃棄物と混載する場合は、中仕切りを使い混ざらないようにし、荷台では転倒や移動を防止する措置も必要です。
また、運搬車の両側面には「産業廃棄物運搬車」であることと、運搬業者の名称・許可番号を見やすい色で表示し、積載するアスベスト廃棄物の内容を記録した管理票を携帯しなければなりません。
厚さ0.15 mm以上のプラスチック袋を使用
アスベスト含有廃棄物を保管・運搬する際は、飛散を防ぐために、散水や発じん防止剤で湿らせることが重要です。そのうえで、強度と防水性を備えた袋や容器に密閉する、またはセメント等で固形化して飛散を防止するなど、適切な処理を行うことが求められます。
使用する袋は、JIS規格に適合する厚さ0.15 mm以上の破れにくいプラスチック袋が望ましく、二重に包むことで飛散リスクをさらに軽減できます。安全性や基準を満たすためにも、信頼できるメーカーが販売しているJIS規格適合の「アスベスト廃棄用袋」を使用するのが安心です。
アスベストを含む一般家庭用品の場合は?
経済産業省の調査結果によれば、過去にはトースターやオーブンレンジ、冷蔵庫など、さまざまな一般家庭用品にもアスベストが使用されていました。もちろん、通常の使用においてアスベストが飛散する恐れはありませんが、処分する際には各自治体の指示に従って適切な方法で処理しなくてはなりません。
自治体によって処理の方法が異なることがありますが、飛散防止のため、基本的に品物は破壊せずそのままの状態で取り扱うことが重要です。また、家庭用品とはいえ無許可で処分することは禁止されており、自治体が委託する専門業者に処理の依頼が必要になる場合もあります。
アスベストを含む廃棄物の中間処理

アスベストを含む廃棄物は、収集・運搬の後、最終処分場へ搬入される前に「中間処理」が行われることがあります。
この工程は、廃棄物の形状や性質に応じて適切に処理し、安全性を確保するために重要で、飛散性の高い「廃石綿等」や比較的安定した「石綿含有一般廃棄物」では、処理方法や必要な対応に部分的な違いがあるので確認しておきましょう。
「廃石綿等」の中間処理
「廃石綿等」は、アスベストが検出されないように高温で溶かす「溶融処理」、もしくは国の認定を受けた業者による「無害化処理」によって処理するのが基本で、これにより一般の産業廃棄物として扱えるようになります。
ただし、無害化できなかった場合は、引き続き特別管理産業廃棄物として厳格な基準のもとで最終処分されます。石綿の飛散を防ぐために二重包装やセメント固化等を施し、許可を受けた管理型最終処分場へと運ばれます。
「石綿含有一般廃棄物」の中間処理
「石綿含有一般廃棄物」も基本的には「廃石綿等」と同様に、高温で溶かす「溶融処理」、もしくは国の認定を受けた業者が行う「無害化処理」によって中間処理が施されます。
また、アスベストの含有量が重量の0.1%以下のものに関しては、他の一般廃棄物と一緒に破砕・焼却できるのが「廃石綿等」と異なるところ。焼却処理は粉じんの発生を防ぐため、排ガス処理設備や集じん器、散水装置などを備えた施設で行われます。
アスベストを含む廃棄物の最終処分

最終的にアスベストを含む廃棄物が行き着く先は、安全に処理・埋立てすることを目的に法令に基づいて設置された専門の最終処分場です。処分場には「安定型」「管理型」「遮断型」の3種類があり、廃棄物の性質や危険性に応じて使い分けられています。
基本的に持ち込まれた廃棄物は、一定の場所にまとめて埋立て、土砂で覆うなどの措置で周囲への影響を防止。アスベストの含有量や廃棄物の状態を問わず、海洋投入処分は一切禁止されています。
【安定型最終処分場】
アスベストを含む廃棄物が「安定型」と認められる場合(有機物を含まないスレートなど)、ここで処分可能です。
特徴:雨などによって有害物質が溶け出す心配がない、比較的安定した性質の廃棄物のみを受け入れます。
対象廃棄物:ガラス、コンクリート、瓦など。
【管理型最終処分場】
有機物を含むものや汚泥状のアスベスト廃棄物など、安定型では処理できない場合はこちらで処分します。
特徴:廃棄物から有害物質が溶け出す恐れがあるため、遮水シートや排水処理設備を備え、周囲への影響を抑える構造になっています。
対象廃棄物:汚泥、プラスチック、焼却灰など。
【遮断型最終処分場】
特にリスクが高い形態で、管理型でも対応できない場合に稀に使用されます。
特徴:極めて危険な有害物質(PCB、ダイオキシンなど)を地中深くに封じ込め、永久に環境と隔離する構造です。
対象廃棄物:処分後も長期にわたって環境リスクがある廃棄物。
「廃石綿等」の最終処分
「廃石綿等」は、厳格な基準のもとで管理型最終処分場など、都道府県知事や政令市の市長から許可を受けた施設で埋立処分されます。
処分前にはアスベストが飛散しないよう、コンクリートで固めたり、薬剤で安定化したりなどの処理を施し、その後、耐水性の高い袋などで二重に梱包。埋立場所も限定され、飛散や流出を防ぐため、表面に土砂をかぶせるなどの措置が義務付けられています。
「石綿含有一般廃棄物」の最終処分
「廃石綿等」と同様に、「石綿含有一般廃棄物」も都道府県知事や政令市の市長から許可を受けた最終処分場にて、飛散・流出しないよう、表面を土砂で覆うなどの措置を講じて埋立処分を行います。
アスベストを含む廃棄物処理での注意点

アスベストを含む廃棄物の処理は、法令で厳格にルールが定められており、適切な対応を怠ると重大なリスクに繋がります。
特に工事現場では、契約内容の不備や処理業者の選定ミス、分別管理の甘さ、マニフェストの管理漏れなど、見落としがちなポイントが多く存在。ここでは、アスベスト廃棄物を安全かつ確実に処理するために押さえておくべき基本的な注意点を解説します。
契約書の明確化
アスベスト含有廃棄物の処理を委託する際には、収集運搬業者や処分業者と個別に正式な契約を結ぶ必要があります。
口頭の取り決めやあいまいな文面では法的な責任の所在が不明確になる可能性があるため、業務内容・責任範囲・処理対象物の種類などを明記した契約書を作成し、保管しておくことが重要です。
処理業者の選定
許可を持っているからといって必ずしも信頼できるとは限りません。許可内容(対象品目やエリア)、最終処分場の残容量、処理施設の設備状況などを複数の業者から確認・比較し、実地確認や見積の精査を行うことが望まれます。選定の責任は、排出事業者にあるという意識を忘れてはいけません。
分別管理の徹底
アスベスト含有廃棄物と非含有の廃棄物を混在させると、法令違反のみならず、処理費用の増加や処理不能といったリスクも生じます。
現場では、仮置きや運搬時に明確な表示を施した容器や梱包材を用い、「アスベスト含有」と分かるようにし、混入を防ぐための管理体制を徹底しましょう。
マニフェストの交付・管理
処理委託時は、廃棄物の流れを把握・管理するためにマニフェスト(管理票)の交付が義務付けられているので注意しましょう。
紙形式の場合、引渡時の交付、5年間の保存、行政報告(年1回)などのルールがあり、電子マニフェストを利用する場合は、引渡し後3日以内の入力が必要です。いずれの場合も記載ミスや未交付は罰則の対象となるため、運用管理を徹底しましょう。
正しい知識と事前分析で廃棄物無駄を最小限に抑える
アスベストを含む廃棄物は、飛散性・非飛散性の違いにより処理方法が異なり、それぞれの特性に応じた対応が求められます。
工事関係者は廃棄物の種類を正しく理解し、収集・運搬から中間処理、最終処分までの一連の流れを把握することが不可欠です。特に「契約書の明確化」「適切な処理業者の選定」「現場での分別管理の徹底」「マニフェストの交付・管理」といった基本的なポイントを見落とすと、法令違反やトラブルに繋がる恐れがあるので気をつけましょう。
また、通常の廃棄物と比べ、アスベスト廃棄物の処分は時間も費用もかかるのが実情です。無駄を最小限に抑えるためにも、信頼できる専門業者に依頼し、事前にアスベストの有無を明確にすることも大切です。
アルフレッドでは、調査費用を極力抑えながらも、スピーディで高精度な調査を実施。安定して土曜日を含む3営業日以内の短納期で分析結果をお出しいたします。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成にも対応。面倒な作業もお任せください!
初回発注の方は最大10検体までの無料キャンペーンを実施中。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。
\ お役に立ちましたら、ぜひ関係者様にシェアをお願いします /
新着記事






