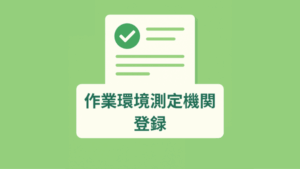知らないと危険!築古の家に潜むアスベスト|安全な改修・解体方法と売買の注意点

築年数の古い住宅には、アスベストを含む建材が今も多く残っている可能性があります。見た目では判断が難しく、知らないまま解体・改修を行うと、健康被害や法令違反となるケースもあるので注意が必要です。
本記事では、住宅に潜むアスベストの特徴や調査方法、工事時の対策、そして予備知識として、売買時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。古い住宅の解体・改修に携わる際には、ぜひ参考にして、リスク回避に努めてください。
【本記事の要約】
・2006年以前に建てられた住宅はアスベスト使用の可能性があり、施行前の調査が義務
・住宅の至る所に使用されている可能性があり、事前調査には有資格者の協力が不可欠
・アスベスト含有した住宅は売買可能だが、使用有無の説明義務がある
- 1. 知っておきたいアスベストと家の基礎知識
- 1.1. アスベストが使用されている家の種類
- 1.2. 家にアスベストが使用された理由と年代
- 1.3. アスベストが潜む家に住んでも大丈夫?
- 1.4. 解体・リフォーム時には調査が義務
- 2. アスベストは家の各所で使用されている
- 2.1. 【屋根】スレート瓦や波板スレートに注意
- 2.2. 【軒天】劣化しやすいケイ酸カルシウム板に注意
- 2.3. 【内装】天井・壁・床材の下地や接着剤にも潜む
- 2.4. 【水回り】浴室やキッチンの断熱材・保温材に残存
- 2.5. 【外壁】窯業系サイディングやモルタル下地に含有
- 2.6. 【その他】屋外構造物の波板や成形板にも残存の可能性
- 3. 家に潜むアスベスト含有建材の見分け方
- 3.1. 設計図書(仕様書や矩計図など)で確認
- 3.2. 専門業者(建築物石綿含有建材調査者)の検査を受ける
- 4. 家の解体や改修前に知っておきたい対策方法
- 4.1. 建材を取り除く除去工法
- 4.2. 完全に覆い隠す囲い込み工法
- 4.3. 固着・固定化する封じ込め工法
- 5. アスベストが残る家の売買
- 5.1. アスベストが残っていても売買可能
- 5.2. 建築物の取引時の説明・表示の必要性
- 5.3. アスベストと重要事項説明
- 6. 家に潜むアスベストは現状把握がリスク回避の第一歩
知っておきたいアスベストと家の基礎知識

アスベストは、耐火・断熱性能に優れた建材として長年住宅に使われてきました。戸建てやアパート、マンションを問わず、2006年以前に建築された住宅では使用されている可能性があります。解体や改修に関わる事業者は、まずアスベストの基礎知識を理解し、工事前に法的義務を踏まえた調査を実施することが不可欠です。
アスベストが使用されている家の種類
アスベストは鉄筋コンクリート造のマンションだけでなく、木造や軽量鉄骨造の戸建て、アパートなどあらゆる住宅構造で使用されてきました。屋根材、外壁、内装ボード、断熱材など用途は多岐にわたり、構造や規模に関係なく、築20年以上(2006年以前)の住宅では使用の可能性があるため注意が必要です。
家にアスベストが使用された理由と年代
高度経済成長期には、アスベストの耐熱性や強度が評価され、住宅建材に広く採用されました。特に1970〜1990年代は、屋根材・外壁材・断熱材に多用され、2006年の全面禁止まで使われ続けたのが実態です。つまり、築20年以上の住宅ではアスベストが残っている可能性が高く、改修や解体の際には調査を行う必要があります。
アスベストが潜む家に住んでも大丈夫?
アスベストは、建材が破損・劣化していなければ飛散しにくく、通常の生活では大きな危険はありません。しかし、経年劣化やリフォームで壁や天井を破ると、粉じんが発生し健康被害を引き起こす恐れがあります。住宅の状態を確認し、必要に応じて専門家の調査を受けることで、安全を確保することが重要です。
解体・リフォーム時には調査が義務
2022年4月の法改正により、建築物の解体・改修工事前には「アスベスト事前調査」が義務化されました。調査は「石綿含有建材調査者」などの資格者が行い、結果は労働基準監督署や自治体へ報告しなければなりません。事業者は工事前の段階で調査を計画に組み込み、法令遵守と安全対策を徹底することが求められます。
アスベストは家の各所で使用されている

アスベストは住宅のあらゆる箇所に使用されてきました。屋根や外壁などの外装部、天井や壁、床などの内装、さらには水回りの断熱材や配管保温材にも含まれている可能性があります。改修や解体を行う際は、構造全体を把握し、どこにリスクが潜むかを事前に特定することが不可欠です。
【屋根】スレート瓦や波板スレートに注意
スレート瓦や波板スレートなど屋根材の多くにアスベストが使用されてきました。特に1970〜1990年代に施工された屋根では使用率が高く、外見だけでは判断が困難です。屋根の張替えや太陽光パネル設置時には、事前調査を行い飛散防止策を徹底する必要があります。
【軒天】劣化しやすいケイ酸カルシウム板に注意
軒天には、石綿セメント板やケイ酸カルシウム板などのアスベスト含有建材が多く用いられました。外気に触れるため劣化が進みやすく、ひび割れや剥がれから粉じんが飛散する危険があります。見た目がきれいでも築年数が古い場合は、専門調査を行うことが安全です。
【内装】天井・壁・床材の下地や接着剤にも潜む
内装では、天井や壁のボード材やビニル床タイル・シート、そして仕上塗材などにアスベストが含まれているケースがあります。特に、天井裏の吹付けアスベスト(レベル1)は飛散性が高く、最も危険度が高いので注意しましょう。
さらに、天井ボード・壁の下地材・接着剤などにもアスベストが混入しているケースもあり、見た目では有無の判別がほぼ不可能です。リフォーム時の穿孔や撤去作業で粉じんが飛散するリスクが高いため、施工前の分析調査が不可欠となります。
【水回り】浴室やキッチンの断熱材・保温材に残存
浴室やキッチンの断熱材、給排水管の保温材などにもアスベストが使用されていました。湿気や熱の影響で劣化が進みやすく、リフォーム時に粉じんが発生する恐れがあるため、古いユニットバスの撤去時には注意が必要です。
【外壁】窯業系サイディングやモルタル下地に含有
住宅の外壁では、窯業系サイディングやフレキシブルボード、外壁モルタルなどに含まれる仕上塗材にアスベストが含まれている場合があります。外装リフォームや塗装時に削り作業を行うと飛散リスクが高まるため、施工前の確認が欠かせません。
【その他】屋外構造物の波板や成形板にも残存の可能性
駐車場の上屋根や物置の屋根の波形スレート板、敷地内の土管、建物の地下ピットなど、屋外構造物にもアスベストが残っていることがあります。解体や撤去の際には、建物本体と同様に調査と飛散防止措置が必要です。
家に潜むアスベスト含有建材の見分け方

外観や触感だけでアスベスト含有の有無を判断することは困難です。設計図書や仕様書の確認、資格者による現地調査、そして必要に応じた分析検査を通じて正確に特定することが重要で、安易な自己判断や未調査の施工は、法的リスクを伴う可能性があります。
設計図書(仕様書や矩計図など)で確認
アスベスト調査の第一歩は、書面調査です。建物の設計図書、竣工図面、仕様書、改修履歴などを集め、使用建材の種類やアスベストに関する記載がないかを確認します。これにより、アスベスト使用の可能性が高い箇所を絞り込んだり、分析調査が不要と判断できたりする場合があります。資料が残っている場合は、この初期確認を必ず行いましょう。
専門業者(建築物石綿含有建材調査者)の検査を受ける
書面調査で特定できない場合や含有の可能性がある場合に実施されるのが、「建築物石綿含有建材調査者」などの資格者による現地調査および分析調査です。現地調査では資格者が建材の設置状況を確認、必要に応じて試料を採取します。採取試料はJIS規格に基づく分析機関で検査され、正式な調査報告書として記録されます。
家の解体や改修前に知っておきたい対策方法

解体や改修工事でアスベストが見つかった場合、建材の状態や飛散リスクに応じた工法を選択する必要があります。代表的な方法には「除去」「囲い込み」「封じ込め」の3種類があり、それぞれの特徴を理解した上で施工計画を立てることが重要です。
建材を取り除く除去工法
除去工法は、アスベスト含有建材を建物から完全に撤去する方法です。アスベスト問題を根本的に解決できるため、解体工事や飛散性の高い建材の処理に主に用いられます。作業には、厳重な隔離養生、負圧管理、作業員の完全防護など、法令で定められた徹底した飛散防止措置が必須です。撤去した廃棄物は特別管理産業廃棄物として厳重に処理・処分されます。
完全に覆い隠す囲い込み工法
囲い込み工法は、アスベスト含有建材の上から、新しい建材などで完全に覆い隠す方法です。アスベスト建材は残りますが、密閉することで繊維の飛散を物理的に防ぎます。除去工法より費用や期間を抑えられるメリットがありますが、建物内にアスベストが残存するため、将来の解体時には改めて除去が必要かつ、定期的な点検と維持管理が欠かせません。
固着・固定化する封じ込め工法
封じ込め工法は、アスベスト含有建材の表面に、固化剤や塗料を吹き付けて固着・固定化する方法です。繊維が空気中に放出されるのを防ぎ、主に飛散性の高いレベル1建材の一時的な対策として用いられます。囲い込み工法と同様に、建材自体は残存するため、恒久的な対策ではない点に注意が必要です。効果を持続させるためには定期的な再塗装などのメンテナンスが不可欠となります。
アスベストが残る家の売買

アスベストが含まれていても、建築物の売買は可能です。ただし、取引時には使用の有無を明確に説明しなければなりません。売主・買主双方にとって安心できる取引を行うためには、調査結果を正確に把握し、適切に情報を開示することが重要です。
アスベストが残っていても売買可能
アスベスト含有建材が使われている建物でも、法令上、売買自体は禁止されておらず、中古住宅として取引を行うことは可能です。ただし、買主にとってアスベストは将来的な解体・改修費用や健康リスクに関わるため、売買価格や交渉に大きく影響します。売主には、後のトラブルを避けるため、調査結果を正確に開示し、透明性の高い取引が求められます。
建築物の取引時の説明・表示の必要性
建築物の取引を行う際は、宅地建物取引業法や住宅品質確保法により、アスベストの使用の有無や対策状況について、買主への説明や表示を行うことが義務付けられています。適切な情報開示は、買主がリスクを正確に認識した上で契約を締結できるようにするために重要であり、売買後のトラブル防止にも繋がります。
アスベストと重要事項説明
宅建業法第35条により、宅地建物取引業者は契約前にアスベスト使用の有無を含む重要事項を書面で説明する義務があります。売主や仲介業者は、調査結果を基に買主へ明確な情報を提供し、トラブル防止に努めることが大切です。
家に潜むアスベストは現状把握がリスク回避の第一歩
アスベストは通常使用では問題ありませんが、建材の劣化や工事の際にリスクが高まります。大切なのは、不安を解消し、リスクを管理するために「正確な現状把握」を行うことです。そのためにも、法律で義務付けられた工事前の事前調査を、有資格者に依頼して確実に行うことが、リスク回避の第一歩となります。専門家と連携を取り、住宅に潜むアスベストの状況を見極めましょう。
アルフレッドでは、調査費用を極力抑えながらも、スピーディで高精度な調査を実施。安定して土曜日を含む3営業日以内の短納期で分析結果をお出しいたします。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成など、面倒な作業もお任せください! 初回発注の方は最大10検体までの無料キャンペーンを実施中です。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。
お役に立ちましたら、ぜひ関係者様にシェアをお願いします /
新着記事