発じん性の高さが危惧される吹き付けアスベスト|特徴や使用場所、対策方法を解説
飛散した繊維を長期間吸入することで、健康被害をもたらす可能性があるアスベスト(石綿)。現在、日本国内では発じん性の高さに応じてアスベスト含有建材を3つのレベルに分類し、“発じん性が著しく高い”とされる建材は、レベル1に認定しています。
この記事では、多種多様なアスベスト含有建材の中でも特に危険度が高い、レベル1の「吹き付けアスベスト」に着目。その種類別の特徴や使用場所、的確な対策方法など、より安全に建築物の解体・改修を着工する上で役に立つ知識を紹介していきます。
【本記事の要約】
・吹き付けアスベストは劣化や損傷によってその繊維が空気中に飛散しやすく、アスベストが含まれる場合は管理が必要
・レベル1に該当する吹き付けアスベスト建材は主に5種類あり、それぞれ特徴や使用されている場所が異なる
・着工には事前調査と結果に応じた対策工事が必要で、自治体によっては補助制度を利用できる
- 1. 慎重な取り扱いが求められる「吹き付けアスベスト等」とは
- 1.1. 吹き付けアスベストがレベル1に認定される理由
- 1.2. 吹き付けアスベストはいつまで使用されていた?
- 1.3. リシンなど今は安全な外壁塗装も年代に注意!
- 1.4. 対象となるアスベストの種類
- 1.5. 全国におけるアスベスト使用建築物の実態調査
- 1.6. 吹き付けアスベストの法規制について
- 2. 「吹き付けアスベスト等」の種類と特徴
- 2.1. 吹き付けアスベスト
- 2.2. アスベスト含有吹き付けロックウール(乾式・半湿式)
- 2.3. 吹き付けロックウール(湿式)
- 2.4. バーミキュライト吹き付け(ひる石)
- 2.5. パーライト吹き付け
- 3. 「吹き付けアスベスト等」の飛散防止に必要なこと
- 3.1. アスベスト飛散の危険度の見極め
- 3.2. アスベスト含有調査
- 3.3. アスベスト飛散防止対策
- 3.4. 吹き付けアスベストの対策に関する補助制度
- 4. 知識と調査で吹き付けアスベスト対策を万全に!
慎重な取り扱いが求められる「吹き付けアスベスト等」とは

吹き付けアスベストとは、アスベストにセメントなどの結合材と水を加えて混合し、壁や天井などに吹き付けた建材。名称に“アスベスト”を含まない「吹き付けロックウール」や「吹き付けひる石」、「パーライト吹き付け」なども、アスベストの含有量が0.1%を超える場合はレベル1に分類される「吹き付けアスベスト等」に該当します。
いずれも耐久性や断熱性、防火性に優れており、主に鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築物の壁や天井、機械室、煙突周辺などに施工されているのが特徴。
木造の戸建住宅で吹き付けアスベストが使用されることは稀でしたが、鉄骨の集合住宅や店舗併設住宅、そこに併設する駐車場などでは、耐火被膜や断熱被膜に使用されているケースもあるため、注意が必要です。
吹き付けアスベストがレベル1に認定される理由
アスベストは固形の状態では人体にほとんど害を及ぼすことはなく、問題視されているのは含有建材の破損や経年劣化によって生じる粉塵の飛散です。これを長期間吸入することが健康被害へとつながるため、アスベスト含有建材の発じん性が重視されています。
レベル2の含有建材も“発じん性が高い”とされていますが、吹き付けアスベストは“著しく高い”のが大きなポイント。
レベル3に該当するスレート波板や石綿含有ボードなどは固形化されているため、通常の使用状態ではアスベストが飛散する可能性は低いですが、吹き付けの場合、多くはアスベストの繊維が露出した状態で施工されます。加えてセメントなどの含有率が少ないこともあり、解体時や経年劣化とともに飛散しやすく、レベル2と比較しても固化などの対策がなされていない場合は発じん性は高いことが多いです。
吹き付けアスベストはいつまで使用されていた?
1956年頃から吸音・断熱用として学校や工場などの天井、壁に、1963年頃からは耐火被覆用としては、鉄骨造建築物のはり、柱に使用されてきました。
1975年に「特定化学物質等障害予防規則」の改正により、アスベストの含有率が5%を超える吹付け作業が原則禁止となりましたが、含有率5%以下である吹き付けロックウールが台頭。最終的に1989年に、全てのアスベストを含有する吹き付け材の製造が中止されました。
リシンなど今は安全な外壁塗装も年代に注意!
リシン・スタッコ・タイルの吹き付けは、現在も使用されている外壁塗装ですが、施工時期によってはアスベストが含まれているので注意が必要です。
国内ではアスベストを配合した、外装塗料を含む建築用仕上塗材製品が1965~1999年に製造されていました。これを受け、建築研究所と日本建築仕上材工業会がアスベスト飛散対策の指針となる報告書「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針」を作成。
この指針には「2006年8月までに施工されたアスベスト含有仕上塗材の改修工事、および解体工事について該当製品が適用される」と、定められています。いずれもアスベストはセメント質や樹脂などの主材と共に凝結しているので通常使用時の危険はありませんが、解体・改修時には的確な対処が必要です。
参考:建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針
対象となるアスベストの種類
アスベストは、天然の繊維状珪酸塩鉱物の総称で、1973年にWHO(世界保健機関)がその分類を「クリソタイル」「アクチノライト」「アモサイト」「アンソフィライト」「クロシドライト」「トレモライト」と定義。
世界の公的機関はこの定義を基本的に踏襲しており、日本でも厚生労働省が「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、及びトレモライト」と定義し、1995年にアモサイトとクロシドライト、2004年にはクリソタイルの製造・輸入・使用が禁止された。他の3種も2006年に0.1重量%を超える製品が禁止され、2012年には全てのアスベストを含む建材の使用が禁止となった。
全国におけるアスベスト使用建築物の実態調査
国土交通省が発表した「民間建築物のアスベスト飛散防止対策に関する調査」によると、1956年から1989年までに施工された民間建築物のうち、1000㎡以上のものを対象に吹き付けアスベストおよびアスベスト含有吹付けロックウールへの2023年度の対応済みの割合は96.2%。22年度と比較しても0.6ポイント増加という高水準な結果となった。
調査対象の25万2045棟のうち、吹付けアスベストなどが露出した状態であると報告された建築物は1万4936棟。このうち指導により対応した建物は1万2391棟、今後対応を予定している建物は477棟となっており、対応の素早さが光る反面、未だ露出した状態の建築物が数多く残されているのが実態です。
吹き付けアスベストの法規制について
建築基準法改正で、含有率が0.1%を超える吹き付けアスベストとアスベスト含有吹き付けロックウールが規制対象となり、以降は建築物への使用が全面禁止に。さらに、2006年以前に建築された建築物の増改築などを行う場合は、除去(既存部分の床面積の2分の1を超えない増改築においては、封じ込め又は囲い込みを許容)などの対策が必要となりました。
他にも、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律をはじめ、労働安全衛生法や大気汚染防止法など、さまざまな法令でアスベストに関する規制は年々厳格化。規制が多岐に渡り、専門知識を要する場面も多いため、刑事罰や罰金などを避けるためにも専門家へ相談するのが安心です。
「吹き付けアスベスト等」の種類と特徴

アスベストの用途は3000種といわれるほど多く、約8割は建材製品として使用されてきました。その中でもレベル1に該当するものは、「吹き付けアスベスト」「アスベスト含有吹き付けロックウール(乾式・半湿式)」「吹き付けロックウール(湿式)」「バーミキュライト吹き付け」「パーライト吹き付け」の5種類です。
ロックウールやグラスウールなど、現在は代用品として特徴が吹き付けアスベストに似た素材が存在するため、見た目で判別するのは困難。施工時期や建材の情報である程度推測はできますが、最終的には分析結果による判断が必要です。
吹き付けアスベスト
石綿とセメントを一定割合で水を加えて混合し、吹き付け施工したもので、1975年頃まで製造。アスベストの種類としては、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト以外に、トレモライトも使われています。
【主な商品名】
ブロベスト、オパベスト、サーモテックスA、トムレックス、リンペット、ノザワコーベックス、ヘイワレックス、スターレックス、防湿モルベストなど
【判断基準】
・表面が綿状で柔らかく、経年劣化などにより石綿の飛散性が高くなる
・石綿の含有率が 60~70%と多い
・アスベスト濃度が高いものは、青色、灰色、白色及び茶色に仕上がっていることが多い。
【使用場所】
・鉄骨耐火被覆材
・天井断熱材
・機械室吸音材
・鉄骨造以外の戸建住宅への使用例は少ない
アスベスト含有吹き付けロックウール(乾式・半湿式)
ロックウールをセメント、アスベストなどと混合し、機械で噴出させ天井などに付着させたもので1987年頃まで製造されていました。ロックウール自体は安全性の高い素材のため、以降も吹き付け材として活用されています。
【主な商品名】
スプレーテックス、スプレーエース、スプレイクラフト、サーモテックス、ブロベストR、ニッカウール、浅野ダイアロック、コーベックスR、スプレーコートなど
【判断基準】
・表面が綿状で柔らかく、経年劣化などにより石綿の飛散性が高くなる
・石綿の含有率が30%以下
・外見は吹き付けアスベストと類似しており、吹き付けアスベストの識別方法に該当しないものは、これである可能性が高い
【使用場所】
・鉄骨耐火被覆材
・天井内壁断熱材
・機械室吸音材
・結露防止用材
吹き付けロックウール(湿式)
ロックウールをセメント、アスベストなどと混合し、機械で噴出させ天井などに付着させた吹き付け材で1987年頃まで製造。耐火・断熱・吸音性に優れ、エレベーターシャフトなどに多く使用されました
【主な商品名】
トムウエット、ATM-120、バルカウェット、プロベストウェット、スプレーコートウェット、サンウェット、スプレーウェット(耐火被膜用)など
【判断基準】
・鉄骨などへの耐火被覆に使用されることが多い
・飛散の度合いは劣化具合いによっては異なる
【使用場所】
・鉄骨耐火被覆材、特にELVシャフト内に多い
・鉄骨造以外の戸建住宅への使用例は少ない
バーミキュライト吹き付け(ひる石)
バーミキュライト(ひる石)をアスベストと混合した吹き付け材で、1988年頃まで製造。内装(天井、壁)の仕上材として、廊下や階段室などで使用されました。
【主な商品名】
ウォールコートM折板用、ミクライト、ゾノライト吸音プラスター、モノコート、パーミックスAP、バーミライトなど
【判断基準】
・表面に粒状の凸凹がある
・黄金色で、光沢がある雲母状の鉱物が確認できる場合がある
・吹き付け材は固化しているため、劣化が進んでいないものは針を刺しても貫通しない
【使用場所】
・天井断熱材
・吸音材
・結露防止用
パーライト吹き付け
真珠岩や黒曜石を焼いて仕上げた軽量の骨材であるパーライトをアスベストと混合した吹き付け材で、1989年頃まで製造。内装(天井、壁)の仕上材として使用されました。
【主な商品名】
ダンコート、アロックなど
【判断基準】
・表面に粒状の凸凹が見られる
・吹き付け材は固化しているため、劣化が進んでいないものは針を刺しても貫通しない
【使用場所】
・内装材の天井梁型、吸音、仕上げ材
「吹き付けアスベスト等」の飛散防止に必要なこと
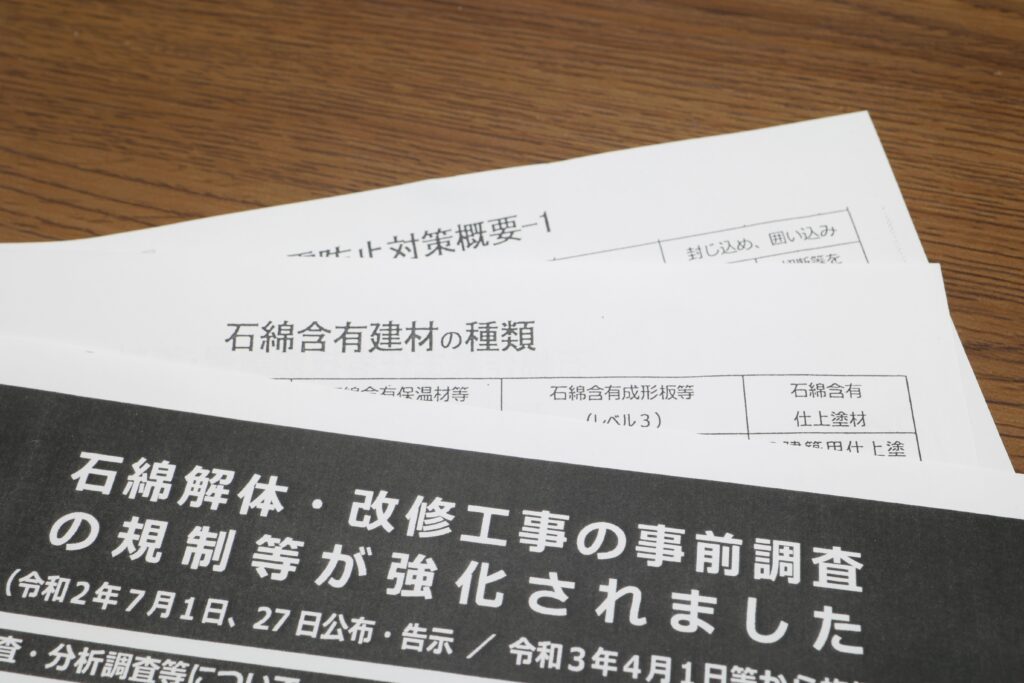
吹き付けアスベストに起因する被害を防止するためには、建築物の所有者・管理者、もしくは施工業者が、建築物における吹き付けアスベストの使用状況や劣化状況を調査・把握し、必要な対策を講じることが重要です。
また、2021年の大気汚染防止法の改正により、当該工事におけるアスベスト含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務化され、さらに2023年には、改修・解体工事におけるアスベスト有資格者の調査が義務化されました。
アスベスト飛散の危険度の見極め
アスベスト混合のセメントは、劣化により表面が毛羽立ちしている場合、結合材なども劣化している可能性が高いので注意が必要です。
毛羽立ちは劣化の初期段階であることが多いものの、さらに劣化が進むと繊維が崩れ、小さな衝撃でも飛び散りやすくなります。
また、アスベストの綿が垂れ下がった状態になるのも劣化を見極める手段の一つ。この状態では飛散する可能性が高いため、迅速な対応が迫られます。
アスベスト含有調査
解体・改修工事を行う際、一定規模の工事の場合は、事前に作業に係る部分の材料について、アスベスト含有の有無の事前調査を行う必要があります。
事前調査は、設計図書等の文書による調査と目視による調査の両方で、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件を満たす専門家による調査が義務なので要注意。2026年1月からは工作物においても同様に義務化されます。
また、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムで報告しなければなりません。
アスベスト飛散防止対策
事前調査の結果を受け、建築物に吹き付けアスベストなどが使用されていることが判明した場合は、アスベスト飛散防止対策を行う必要があります。
将来の安全も考えてアスベストの飛散を完全に防止するなら除去工法がベストですが、工期や費用によっては、一時的な対策として封じ込め工法や囲い込み工法での対策も考えられます。アスベストの施工場所、周辺環境なども考慮して、適した対策を選びましょう。
【除去工法】
吹き付けアスベストを下地から取り除く抜本的解決方法。工期が長く費用が高めですが、その後はアスベスト含有建材が完全に除去されるため、将来的に解体・改修工事を行う際に影響が及ぶこともありません。
【封じ込め工法】
吹き付けアスベストの層を残したまま、薬剤などを含浸したり、造膜材を散布し、吹き付けアスベストを固定することで飛散を防止します。除却工法より安価で工期も短いですが、根本的解決に至っていないため、定期的なアスベストの点検・管理が必要。さらに、建築物の解体時には除却工事が必至です。
【囲い込み工法】
板状の材料で吹き付けアスベストの層を覆うことで、粉塵の飛散や損傷防止などを図る工法。封じ込め工法と同様に除却工法より安価で工期も短いですが、定期的なアスベストの点検・管理と、建築物の解体時には除却工事が必至となります。
吹き付けアスベストの対策に関する補助制度
補助制度がある地方公共団体においては、民間建築物に対するアスベストの調査、飛散防止工事に関して、制度を活用できる場合があります。
国土交通省が2024年1月に公表したデータによると、補助制度創設済みもしくは融資等を用意している都道府県は16。さらに19の政令市が補助制度を創設しています。また、政令市以外の市区町村でも制度を活用できるところもあるので、事前に所轄の地方公共団体に確認してください。
知識と調査で吹き付けアスベスト対策を万全に!
一般住宅ではあまり使用されていないものの、学校や工場、商業施設など、耐火性や防音性が高いことから、人が多く集まる場所に使われてきた吹き付けアスベスト。
アスベストの短繊維は髪の毛の5000分の1ほどの繊維のため、ばく露しても感覚的に察知できないのが怖ろしいため、信頼できる専門家に事前調査を依頼し、アスベスト含有の有無を明確にすることが大切です。
アルフレッドでは、高精度な分析を実施。安定して土曜日を含む3営業日以内の短納期で分析結果をお出しいたします。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成にも対応。面倒な作業もお任せください!
初回発注の方は「最大10検体までの無料キャンペーン」を実施中。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。



