アスベスト(石綿)とは?健康被害を防ぐため法規制が強化
アスベスト(石綿)は様々な機能を持ちながら安価で扱いやすいことから、多様な建築資材の原料となり、多くの建築物に使用されてきました。
アスベストを長期間吸い込むことが健康被害につながると判明し、現在は使用が禁止されています。しかし、過去にアスベストを使用した建物の解体・改修工事を行う際、アスベスト曝露を防ぐことが喫緊の課題となっています。
この記事では、アスベストの種類や性質、これまでの建築での使用用途、健康被害のリスク、そして強化されていくアスベストの法規制について紹介します。
【本記事の要約】
・柔軟性があり、熱や酸・アルカリに強いアスベストは建築資材に多用された
・アスベスト繊維は微細で人体に吸入されやすく、長期ばく露は健康を損なうおそれがある
・アスベストが使用された建築物の解体・改修工事に関する法規制の強化が進んでいる
- 1. アスベスト(石綿)とは?
- 1.1. アスベストとは何かを簡単に説明
- 1.2. アスベストの種類と特性
- 1.2.1. クリソタイル(白石綿)
- 1.2.2. アモサイト(茶石綿)
- 1.2.3. クロシドライト(青石綿)
- 2. アスベストは建築にどう使われてきたか
- 2.1. 建築業界等でのアスベスト使用の歴史
- 2.2. アスベストが使用されていた建築資材とその理由
- 3. アスベストによる健康被害
- 3.1. アスベストばく露で発症する主な病気
- 3.1.1. 石綿(アスベスト)肺
- 3.1.2. 肺がん
- 3.1.3. 悪性中皮腫
- 4. アスベストに関する主な法規制
- 4.1. アスベスト建材の製造・使用における法規制
- 4.2. 建築物の解体・改修工事における法規制
- 5. 建築物の解体・改修工事にはアスベスト含有の事前調査と適切な取り扱いが必要
アスベスト(石綿)とは?

日本では「石綿(せきめん/いしわた)」とも呼ばれるアスベスト。天然の鉱物で、加工しやすく丈夫な素材であることから、かつては「奇跡の鉱物」といわれ建築資材に多用されてきました。ここでは、その種類や特性を解説します。
アスベストとは何かを簡単に説明
アスベストは天然に産出する繊維状の鉱物です。熱、摩擦、酸・アルカリに強く、丈夫で扱いやすい特性があり、断熱材や保温剤、防音材として幅広い建築資材に使用されてきました。
アスベストの繊維は非常に細かいために飛散しやすく、人体に吸入されると健康被害につながるおそれがあることが問題となっています。1950年代から建材として使用されていたアスベストですが、1972年には国際労働機関(ILO)や世界保健機構(WHO)が発がん性を指摘しました。1975年以降、段階的に規制が始まり、現在は使用・製造ともに禁止されています。
アスベストの種類と特性
アスベストは「蛇紋石族」と「角閃石族」の2つに大別され、全部で6種類あります。その中でも日本で使用された代表的な3種類のアスベストは以下になります。
クリソタイル(白石綿)
6種類のアスベストの中で唯一「蛇紋石族」に属します。最も細く、微弾性、柔軟性に優れることから、多くののアスベスト製品の原料に用いられてきました。世界で使用されたアスベストの9割以上を占めます。
アモサイト(茶石綿)
茶石綿とも呼ばれる通り、灰〜淡褐色をしているのが特徴で「角閃石族」に属します。クリソタイルよりも耐熱性や耐酸性に優れ、断熱保温材として吹き付け材や煙突断熱材に使用されてきました。
クロシドライト(青石綿)
青色をしたクロシドライトは「角閃石族」に属します。柔軟性、耐酸性、耐アルカリ性に優れ、吹き付け材のほか、水道用高圧管や耐酸性シール材などにも使用されました。発がん性はクリソタイル、アモサイトよりも強いといわれています。
上記以外に、アンソフィライト石綿、トレモライト石綿、アクチノライト石綿があります。
アスベストは建築にどう使われてきたか

アスベストは安価で加工しやすい素材として、1950年代から2000年頃まで様々な建築資材に使用されてきました。建築業界での使用の歴史と、使用された多様な建材について紹介します。
建築業界等でのアスベスト使用の歴史
アスベストを使った建築資材は、1950年代から使われ始めたといわれています。アスベストとセメントに水を混合した吹き付け材は1975年に原則禁止となりましたが、ロックウールやパーライトなど、他の鉱物に含まれた吹き付け材は1989年まで使用が続きました。
珪藻土やバーミキュライトなど天然鉱物等とアスベストを原料にした保温材は多数あり、1980年頃まで使用されました。また、スレートボードなどの内装材や、サイディング、スレートなどの外装材には2004年頃まで使用された歴史があります。
アスベストが使用されていた建築資材とその理由
低コストで様々な建築資材へと加工できるアスベストの用途は約3,000種に及ぶといわれています。鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築物では、内装材や外装材、屋根材、配管と多くの部位に使われました。
断熱性、防音性が高いことから吹き付け材として天井などに使われた他、配管エルボ、ボイラーなどの保温材にもなっています。アスベスト建材は軽量で耐火性にも優れるため、柱、梁、壁、天井の耐火被覆材となり、スレートボードやフレキシブル板として外壁や軒天にも使われました。
戸建て住宅では外壁のサイディングに使われた他、キッチンなどのビニル床タイルやシート、せっこうボードや壁紙など内装材としても多くのアスベスト建材が使用されています。
アスベスト建材が製造された時期は概ね把握できるため、建物の施工時期によってアスベスト含有の有無を推測できる可能性があります。
アスベストによる健康被害

アスベストの繊維は非常に細く、人の髪の毛の直径約40 μmに対し、クリソタイルの直径は0.02〜0.08 μmと肉眼では確認できないほどです。アスベスト自体に毒性はありませんが、飛散すると空気中に浮遊しやすく、人体に吸入されると長く滞留し肺がんなどの病気を引き起こす可能性があります。発症までの潜伏期間が長いため、アスベストは「静かな時限爆弾」と呼ばれ、アスベスト建材の施工に従事した人は、今後も健康状態の変化に留意する必要があります。。また、建築物を解体・改修する際は、事前にアスベスト含有の有無を調査し適切な措置を講じることで、作業者や近隣住民の健康被害を防ぐことが重要です。
アスベストばく露で発症する主な病気
石綿(アスベスト)肺
肺が繊維化する「じん肺」という病気の一つで、アスベストばく露によって発症したものを「石綿肺」と呼んでいます。咳、息切れなどの初期症状から呼吸困難へと至ることがあります。職業上アスベストばく露を10年以上受けた作業者に発症するといわれ、潜伏期間は10〜20年ほどです。
肺がん
喫煙など他の要因によっても発症し、症状や治療方法などに違いはありません。喫煙との関係が知られており、アスベストと喫煙の両方のばく露を受けると発症リスクが相乗効果で高くなるといわれています。潜伏期間は15〜40年で、咳や痰などの症状がみられます。
悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などを囲む腹膜、心臓や大血管の起始部を覆う心膜などにできる悪性の腫瘍です。潜伏期間は40〜50年と長いのが特徴ですが、石綿肺・肺がんと比べ低濃度のばく露でも発症する可能性があり、家庭内や近隣でのばく露による発症もあります。胸膜中皮腫では息切れや胸痛、咳など、腹膜中皮腫では腹痛や腹部膨満感などの症状がみられます。
アスベストに関する主な法規制
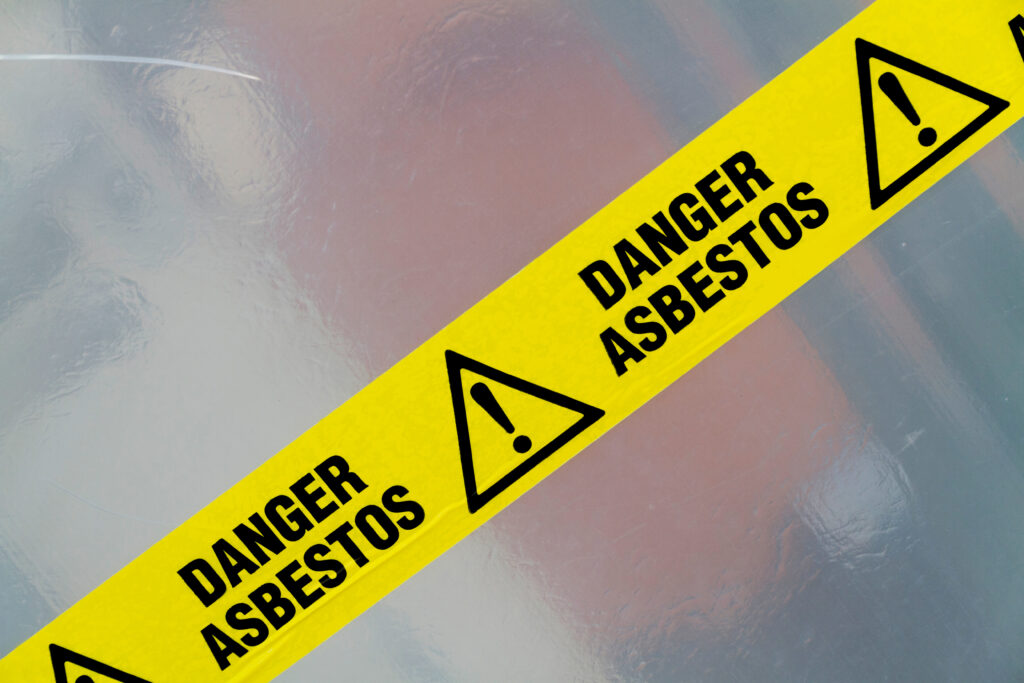
アスベストばく露によって健康を損なうおそれがあるとわかって以降、様々な法規制が整備されました。1975年から始まったアスベスト建材の製造・使用における法規制と、近年強化が続く建築物の解体・改修工事における法規制の2つに分けて、主な法規制を見ていきましょう。
アスベスト建材の製造・使用における法規制
1975年、アスベスト含有率が重量の5%を超える製品の吹き付け作業が禁止されたのを皮切りに、アスベストに関する法規制が整えられました。1995年にはアモサイト、クロシドライトの製造、輸入、使用が禁止されるとともに、アスベスト含有率1%を超える製品の吹き付け作業が禁止になりました。2006年になると、アスベスト含有率0.1%を超える製品の製造、輸入、使用などが禁止と規制が強化されました。
建築物の解体・改修工事における法規制
1989年、アスベストが「特定粉じん」に指定されました。1995年、吹き付けアスベスト除去場所の隔離、呼吸用保護具や保護衣の使用、解体工事におけるアスベスト使用状況の事前調査結果の記録が始まります。
2020年になるとアスベスト含有の事前調査方法の法整備が進みました。2021年からは建物の解体・改修をする際、アスベスト含有の有無を調べる事前調査が義務化されました。また、アスベスト含有建材の除去がある場合は工事の14日前までに届出が必要です。2023年からは、事前調査は厚生労働大臣が定めた講習を修了した者が行うと定められました。
建築物の解体・改修工事にはアスベスト含有の事前調査と適切な取り扱いが必要
安価で建築資材として優れた特性を持つアスベストは、日本でも長期間にわたり製造・使用されてきました。微細な繊維であることから人体に吸入されやすく、健康被害につながることが明るみになり、製造や使用が禁止された今も、解体・改修工事においてアスベストは大きな問題です。
工事従事者や近隣住民がアスベストばく露による健康被害に遭わないため、有資格者による事前調査は必須となります。2006年以前に建築された建物の工事が必要になった場合は、必ず専門機関にアスベスト含有有無の調査を依頼し、アスベストの飛散やばく露の防止対策を取ることが必要です。
アスベスト分析を依頼する際には、依頼する調査機関の品質(分析精度)に注意する必要があります。アルフレッドでは、分析における見落としなどが生じないための、分析プロセスや最新のITシステムを導入しております。詳細は以下のラボ紹介動画からぜひご覧ください。
また、99.998%の驚異的な納期遵守率による安定した納期や現場からスマホで発注ができる「アルモバ」サービスをご体感いただくためにも、初回最大10検体までの無料キャンペーンも行っております。これを機に、ぜひお試しください。



