【2025年最新版】施行時期や改正内容など法律から学ぶアスベスト対策
耐火性や断熱性、防音性、絶縁性などに優れ、安価で入手できることから、かつては建材製品や工業製品の材料として重宝されていたアスベスト(石綿)。しかし、粉じんを長期に渡って吸入することで健康被害をもたらすことが社会問題となり、現在、日本国内では含有製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用において、全面的に禁止となっています。
さらに、アスベストが使用されている建築物・工作物の解体や改修作業に関しても、様々な法律で段階的に規制されており、その成果を検証しながら、現在も法改正が行われています。
この記事では、規制強化に伴って繁雑になるアスベスト法の変遷や種類、近年の改正内容を整理して解説。アスベストに関わる多くの方の安全のため、そして関連企業のリスクヘッジのためのガイドとして参考にしてください。
以下のお役立ち情報ではアスベスト関連の法律に関して、図解化した資料をご用意しております。ぜひご活用ください。
お役立ち情報 「2025年版 アスベストの最新規制動向」
お役立ち情報「1960~2020年のアスベスト関連法令とその変遷」
【本記事の要約】
・建築物の解体・改修に携わる上で、覚えておきたいアスベスト法の種類と変遷が分かる
・大気汚染防止法と労働安全衛生法の改正により、2021年以降、段階的に施行された規制、並びに2025年以降に施行される規制を読み解く
・アスベスト飛散による法的リスクを理解し、的確なリスクマネージメントを考える
- 1. アスベストに関する主な関係法令
- 1.1. 建築基準法|国土交通省
- 1.2. 労働安全衛生法(石綿障害予防規則を含む)|厚生労働省
- 1.3. 大気汚染防止法|環境省
- 1.4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)|環境省
- 1.5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)|環境省
- 1.6. 宅地建物取引業法(略称:宅建業法)|国土交通省
- 1.7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律|国土交通省
- 2. 使用禁止はいつから?アスベスト関係法規の変遷
- 3. 2021年以降は段階的に強化
- 3.1. 2021年4月1日施行|レベル3建材も規制対象へ追加など
- 3.2. 2022年4月1日施行|アスベスト事前調査結果の報告の義務化
- 3.3. 2023年10月1日施行|有資格者による調査報告が義務化
- 3.4. 2024年4月1日施行|除じん性能を有する電動工具の使用
- 3.5. 2025年4月1日施行|安全に作業できる環境の整備
- 3.6. 2026年1月1日施行|工作物の解体等工事を行う場合の事前調査の義務化
- 4. アスベスト飛散による法的リスク
- 4.1. 調査や報告を怠った場合
- 4.2. 作業実施の届出に違反した場合
- 4.3. 作業基準に違反した場合
- 5. 法律遵守で社会的信用を失わないためには
アスベストに関する主な関係法令

一般的に「アスベスト法」と呼称表記されることがありますが、これはアスベスト規制に関する法律の総称。実際は、厚生労働省や環境省、国土交通省を中心に複数の省庁がそれぞれの法律のもとで包括的に管理しています。
その種類はアスベストの使用や製造に関するものから、ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止、廃棄物の処理に至るまで実に様々。いずれも改正される可能性があるため、アスベスト含有建築物に携わる企業・事業者は、常に規制動向に目を光らせる必要があります。
建築基準法|国土交通省
吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕や模様替の際に除去を義務づけている法律です。状況によっては除去ではなく、封じ込めや囲い込みによる対応を許容しています。
【主な規制内容】
①建築材料へのアスベスト等の添加及びあらかじめ添加した建築材料の使用禁止
②増改築時における除去などを義務付け
③飛散の恐れのある場合に勧告・命令などを実施
④報告聴取・立入検査を実施
⑤定期報告制度による閲覧の実施
労働安全衛生法(石綿障害予防規則を含む)|厚生労働省
労働者の健康を保護するために、アスベスト含有量が重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用を全面的に禁止。さらに、アスベストを取り扱う作業における安全基準も定めています。
【主な規制内容】
①アスベスト及び、アスベストを重量の0.1%を超えて含有する全ての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止
②アスベストによる健康被害が疑われる場合には、労働者は職業病として報告する権利があり、事業主の適切な対応を義務化
③石綿障害予防規則の制定により、建築物の解体等の作業におけるアスベストばく露防止対策などについて規定
④吹付けアスベストの除去などに係る隔離措置や建築物に使用されているアスベスト含有保温材等の管理について規制
⑤建築物の解体など、作業及び労働者がアスベストにばく露するおそれがある業務での労働者のばく露防止に関する技術上の指針を制定
大気汚染防止法|環境省
建築物などの解体や改造、補修作業に伴う大気汚染を防止し、作業及び労働者の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的とした法律。建築物解体などの作業の届出、建築物解体などの作業基準を規定しています。
【主な規制内容】
①建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめアスベスト含有材料の使用の有無の事前調査を規定
②一定規模以上の建築物または工作物の解体工事などにおいて、アスベスト使用有無の調査結果の報告を義務化
③アスベスト含有建材が使用されている建築物等の解体や改造、補修をする際に、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」を制定
④吹付けアスベスト、アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業について、作業を実施する14日前までに都道府県への届出を規定
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)|環境省
分別解体などに係る施工方法に関する基準として、建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずることなどを規定しています。
【主な規制内容】
①コンクリートなどの特定建設資材に付着した吹付けアスベスト等の有無など、対象建築物に関する調査
②特定建設資材に付着した吹付けアスベスト等の有無や除去などの措置、その他計画などについて届出書への記載
③特定建設資材に付着した吹付けアスベスト等の除去など、特定建設資材を適正に分別解体するための措置
④特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別するため、事前措置を含め解体工事などの計画的な施工
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)|環境省
アスベストを含有する廃棄物について、「廃石綿等」または「石綿含有一般廃棄物」、「石綿含有産業廃棄物」として厳格な処理を行うことを規定。産業廃棄物の収集、運搬および処分に関する基準も制定しています。
【主な規制内容】
①廃棄物の運搬・保管に関して、他の廃棄物との区分と飛散防止措置を要する規定
②溶解・無害化処理ができない場合は最終処分場に搬入するなど、中間処理に関する規定
③廃棄物は埋め立てを最終処分とし、都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市の市長に許可を受けた最終処分場で行うことを規定
宅地建物取引業法(略称:宅建業法)|国土交通省
売買の対象となる建築物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として契約の成立前までに建物の購入者などに説明することを規定しています。
住宅の品質確保の促進等に関する法律|国土交通省
住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、「アスベスト含有建材の有無等」などを規定しています。
使用禁止はいつから?アスベスト関係法規の変遷

日本国内におけるアスベストを規制する法律は、1960年に制定された「じん肺法」が原点。当時はアスベスト特有のリスクに焦点が当てられたわけではなく、労働環境におけるほこりの管理を通じて、労働者のじん肺症を予防するのが目的としていました。
その後、1970年代から本格的な規制が始まり、その実態が明らかになるに連れ、関連する法律を厳格化。度重なる強化と改正を繰り返し、今日に至ります。
現行法を学ぶことももちろん大切ですが、そこに行き着くまでの変遷を知ることも、アスベスト法への理解を深めるために欠かせません。
・1960年〜2020年の石綿関係法規の変遷
年号 | 法規、通達名 | 法規・通達の概要 |
| 1960年 | 「じん肺法」制定 | じん肺健診についての規定 (石綿も対象) |
| 1971年 | 「労働基準法特定化学物質等障害予防規則」(特化則)制定 | 製造工場が対象、局所排気装置の設置、作業環境測定の義務付け(測定方法の規定なし) |
| 1972年 | 「労働安全衛生法(安衛法)」制定、「特化則」再制定 | 安衛法が新たに制定され、特化則は同法に基づく規定に |
| 1975年 | 「労働安全衛生法施行令」 (安衛法施行令)の改正 | 名称等表示 (アスベスト5%超対象) |
| 「特化則」の大改正(1970年 ILO職業がん条約批准のため) | アスベスト5%超対象、取扱い作業も対象、アスベスト等の吹付け作業の原則禁止、特定化学物質等作業主任者の選任、作業の記録、特殊検診の実施、掲示など | |
| 1988年 | 「作業環境評価基準」(厚生労働省告示)制定 | 法規に規定されている各種物質の管理濃度を規定 (アスベストも対象:2f/cm3) |
| 1999年 | 「大気汚染防止法(大防法・同) 施行令・同施行規則」の改正 | アスベストを特定粉じんとし、特定粉じん発生施設の届出、アスベスト製品製造/加工工場の敷地境界基準を10 f/Lと規定 |
| 1991年 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (廃棄物処理法)の改正 | 特別管理産業廃棄物として「廃石綿等」を新たに制定。吹付けアスベスト、アスベスト含有保温材などのアスベストを含有する廃棄物が該当 |
| 1995年 | 「安衛法施行令」の改正 | アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)の製造等禁止 |
| 「労働安全衛生規則」(安衛則)の改正 | 吹付けアスベスト除去作業の事前届出 | |
| 「特化則」の改正 | アスベスト1%超まで対象が拡大、 吹付けアスベスト除去場所の隔離・呼吸用保護具及び保護衣の使用、解体工事におけるアスベスト使用状況の事前調査結果の記録 | |
| 1996年 | 「大防法」の改正 | 特定建築材料(吹付けアスベスト)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出、作業基準の遵守義務を規定 |
| 1997年 | 「大防法施行令・同施行規則」の改正 | |
| 1999年 | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」制定 | 特定第一種指定化学物質としてアスベストが規定され、年間500 kg以上使用する場合に、環境への移動・排出量を国への報告義務付け |
| 2004年 | 「安衛法施行令」の改正 | アスベスト含有建材、摩擦材、接着剤など10品目が製造など禁止 |
| 「作業環境評価基準」(厚生労働省告示)の改正 | アスベストの管理濃度を改正(施行期日2005年4月1日) | |
| 2005年 | 「石綿障害予防規則」 (石綿則)の制定 (施行期日:2005年7月1日) | 特定化学物質等障害予防規則から、 アスベスト関連を分離し、 単独の規則であるアスベスト障害予防規則を制定。解体 ・ 改修での規制(届出、特別教育、アスベスト作業主任者など)を追加 |
| 「大防法施行令・同施行規則」 の改正 (施行期日: 2006年3月1日 ) | 吹付けアスベストの規模要件などの撤廃と特定建築材料にアスベスト含有保温材、 耐火被覆材、断熱材が追加。掻き落し、破砕などを行わない場合の作業基準を規定 | |
| 2006年 | 「大防法」の改正 (施行期日:2006年10月1日) | 法対象の建築物に加え工作物も規制対象となる |
| 「安衛法施行令」の改正 (施行期日:2006年9月1日) | アスベスト0.1重量%超の製品の全面禁止(一部猶予措置あり) | |
| 「石綿則」の改正 (施行期日:2006年9月1日) | 規制対象をアスベスト0.1重量%超に拡大一定条件下での封じ込め、囲い込み作業に対する規制の強化など | |
| 「廃棄物処理法」の改正 (施行期日:2006年10月1日) | アスベス0.1重量%超を含有する廃棄物(廃アスベストなどを除く)をアスベスト含有廃棄物と定義、無害化処理認定制度が発足(施行期日2006年8月9日) | |
| 2008年 | 「石綿則」等の一部を改正する省令等 (施行期日:2009年4月1日) | ・隔離の措置を講ずべき作業範囲の拡大、隔離の措置等 |
| ・事前調査の結果の掲示 | ||
| ・吹付けアスベスト除去作業について電動ファン付き呼吸用保護具着用を義務づけ | ||
| ・船舶の解体などの作業に係る措置(施行期2009年7月1日) | ||
| 2011年 | 「石綿則」の一部を改正する省令(施行期日: 2011年8月1日) | 船舶の解体などについて、建築物解体などと同等の措置を義務付け |
| 2012年 | 「安衛法施行令等」 の一部を改正する政令 (施行期日:2012年3月1日) | アスベスト0.1重量%超の製品の製造等禁止の猶予措置を撤廃 |
| 2013年 | 「大防法」の改正 (施行期日:2014年6月1日) | 届出義務者を発注者に変更、解体等工事の事前調査及び説明の義務化、作業基準の改正 |
| 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」(国土交通省告示) | 建築物の通常使用におけるアスベスト含有建材の使用実態の把握推進のため、 同規定を創設 | |
| 2014年 | 「石綿則」の一部を改正する省令(施行期日:2014年6月1日) | 負圧状態の確認、損傷・劣化など、アスベスト粉じん発散のおそれがある保温材などの集じん・排気装置の排気口からの石綿漏えいの有無の点検、作業場前室の除去などの対応の追加 |
| 2017年 | 「石綿含有仕上塗材の除去等作業における飛散防止対策について通知」(環境省) | アスベスト含有仕上塗材の除去作業における飛散防止対策について、吹付け工法で施工されたものについては吹付けアスベストとして扱うこととした |
| 2018年 | 「安衛法施行令」、「安衛則」の改正(施行期日:2018年6月1日) | 分析、教育用のアスベストの製造・輸入・使用などを可能とした |
| 「石綿則」の一部を改正する省令(施行期日:2018年6月1日) | アスベスト分析用試料などの定義、製造に係る措置、製造許可、届出などを規定 | |
| 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」(厚労省・国交省・環境省告示) | 3省連携により、国交省の旧規定の内容に解体時の事前調査に必要な知識を追加 | |
| 2020年 | 「大防法」の改正 (施行期日:一部除き2021年4月1日) | すべての建材への規制拡大及び作業基準の適用、 事前調査方法の法定化・資格者による事前調査の実施、 事前調査結果の記録の保存及び都道府県への報告の義務付け、 取り残しなどの確認及び記録の保存の義務化、 直接罰の創設など |
| 「石綿則」の一部を改正する省令(施行期日:一部除き2021年4月1日) | 事前調査及び分析調査を行う者の要件の新設、 計画届の対象拡大、 事前調査結果の届出制度の新設、隔離(負圧不要)を要する作業に係る措置の新設、その他作業に係る措置の強化、作業計画に基づく記録・保存の義務化、アスベストの有無が不明な建材に対してアスベストが使用されているものとみなして工事を行うことにより分析調査を不要とする規定を吹付け材にも適用など | |
| 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」の一部改正(厚労省・国交省・環境省告示) | 一戸建てなど、アスベスト含有建材調査者の講習規程を新設 |
引用:「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」表2.1.1 石綿関係法規の変遷|環境省
2021年以降は段階的に強化
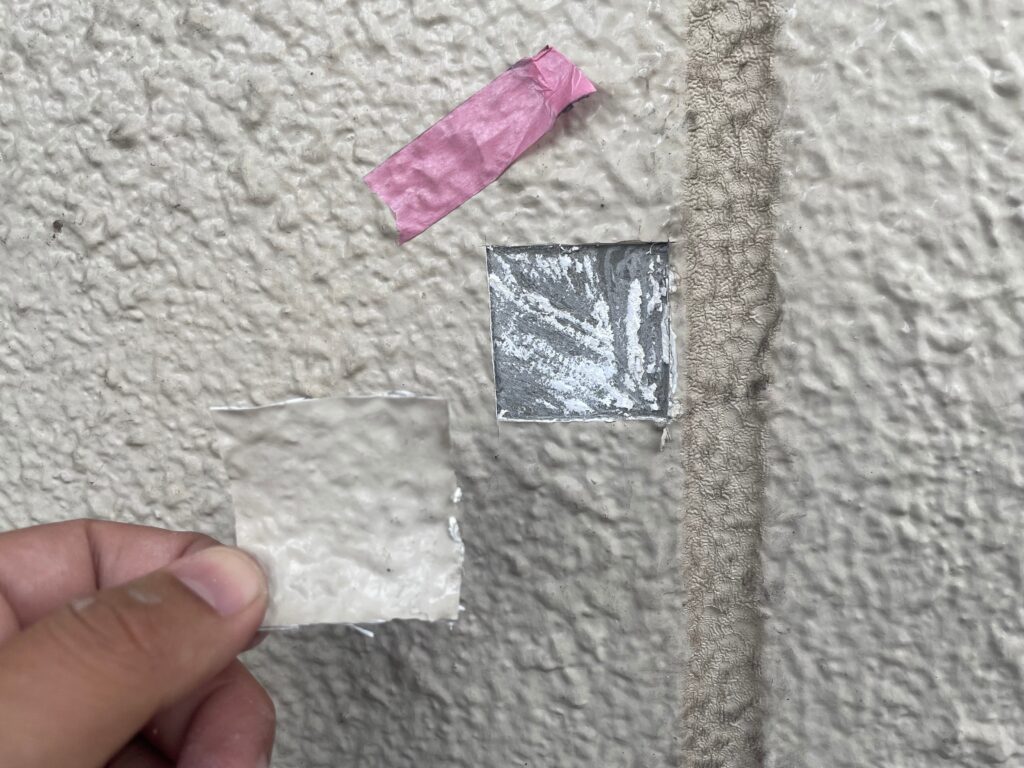
近年のアスベストの規制動向で注意すべきは、2020年に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律が、2021年から段階的に施行されている点です。
毎年、新たな改正案が施行されていくため、建築物の解体・改修に携わる企業や事業者は対応が急務。さらに2025年、2026年に施行されるものもあるので、今一度、2021年以降の変更点を確認しておきましょう。
2021年4月1日施行|レベル3建材も規制対象へ追加など
それまで規制外であったレベル3のアスベスト含有建材も規制対象になったことをはじめ、
事前調査や工事終了後の確認も厳格化されるなど、改正内容は多岐に渡ります。
【改正のポイント】
①レベル3を含む、全てのアスベスト含有建材に規制対象が拡大。ただし、レベル3に該当するアスベスト含有成形板等や、アスベスト含有仕上塗材に係る工事については対象外です。
②建築物の解体、改修など、工事対象となる全ての材料について、アスベスト含有の有無を設計図書などの文書と目視で調査し、その調査結果の記録を3年間保存することが義務付けられました。
③吹付けアスベストに加え、アスベストが含まれる保温材などの除去などの工事は14日前までに労働基準監督署に届出が必要となりました。
④除去工事終了後、「石綿作業主任者、事前調査に必要な知見を有する者」により、取り残しがないかの確認が必要となりました。
⑤アスベストを含む仕上塗材をディスクグラインダーなどで除去する工事において、作業場の隔離が必要になりました。
2022年4月1日施行|アスベスト事前調査結果の報告の義務化
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果などを行政に報告することが義務付けられました。
【報告対象となる工事】
① 解体部分の延べ床面積が80 ㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
2023年10月1日施行|有資格者による調査報告が義務化
すべての建築物において、解体・改修前の事前調査を建築物石綿含有建材調査者等が行うことが義務付けられました。
2024年4月1日施行|除じん性能を有する電動工具の使用
除じん性能を備えた電動工具の使用が、アスベストを湿潤化した場合と同等以上の粉じんの発散低減効果があることから、アスベスト含有建材などの切断作業において、除じん性能を有する電動工具の使用が義務付けられました。
2025年4月1日施行|安全に作業できる環境の整備
労働安全衛生規則等の一部改正により、立入禁止、退避などの安全措置の対象範囲が「労働者」から「作業に従事する者」に拡大されます。これにより、アスベストを取り扱う現場での表示義務や有害性に関する警告などは、直接契約の有無に関わらず、労働者以外の作業者にも周知が必要です。
2026年1月1日施行|工作物の解体等工事を行う場合の事前調査の義務化
建築物、船舶に対するアスベスト事前調査に加え、一部の特定工作物についても、新たに指定された「工作物石綿事前調査者」による事前調査が義務化されます。
【対象となる特定工作物】
反応槽/加熱炉/ボイラー及び圧力容器/配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建設設備を除く)/焼却設備/煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く)/貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)/発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)/変電設備/配電設備/送電設備(ケーブルを含む)/トンネルの天井板/プラットホームの上家/遮音壁/軽量盛土保護パネル/鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板/観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)
アスベスト飛散による法的リスク

アスベストの除去作業は、建築物の所有者や工事関係者に思わぬリスクをもたらすことがあります。特に、解体や改修作業に伴う処理費用は高額になりがちで、予期せぬトラブルが生じることも少なくありません。
さらに、対応を誤ると法的責任を問われる可能性があるため、事前のリスク評価と適切な対策が求められます。
調査や報告を怠った場合
アスベストの事前調査報告を怠った場合や虚偽の報告を行った場合には、大気汚染防止法の規定により、30万円以下の罰金が科されます。
また、故意にアスベストの調査を怠るなどで周囲の健康被害が発生した場合、刑事罰として懲役刑が科される他、施主様や労働者から損害賠償請求を受ける可能性もあるので注意が必要です。
作業実施の届出に違反した場合
特定粉じん排出など作業の実施の届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、直接罰の対象となります。
罰則は、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金。また、災害その他非常事態の発生により特定粉じん排出など、作業を緊急に行う必要がある場合において届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
作業基準に違反した場合
適切な隔離などをせずにアスベストの除去作業を行ったり、法律で定められた方法で作業を行っていない場合は、直接罰の対象となります。
罰則は3か月以下の懲役または30万円以下の罰金で、作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時停止命令が出されることも。さらに、上記の命令に違反した際は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
法律遵守で社会的信用を失わないためには
建築物や工作物の解体・改修に携わる企業や事業者にとって大切なのは、多岐に渡るアスベストに関する法律を理解し、厳守することです。
わずかな違反によって、現場の作業員や関係者、そして周辺の人々の健康を脅かす結果に繋がるのはもちろん、企業や事業者としての社会的信用さえも一気に失うことになってしまいます。
とはいえ、常に変わり続けている法律の内容を全て把握し続けるのは難しいところ。部分的には専門組織に頼るのが安心です。
アルフレッドは、最新鋭の分析設備・ITシステムを備えたラボで、高精度な分析を実施。土曜日を含め、安定して3営業日以内に分析結果をご提供。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成にも対応しています。
初回発注の方には、最大10検体までの無料キャンペーンを実施中です。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。




